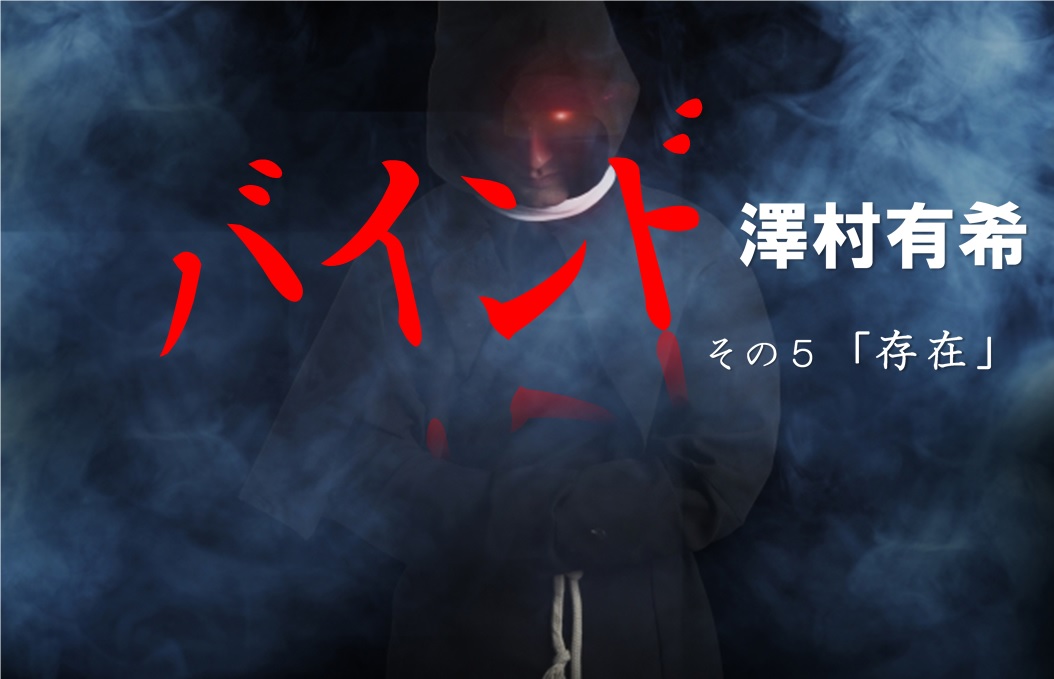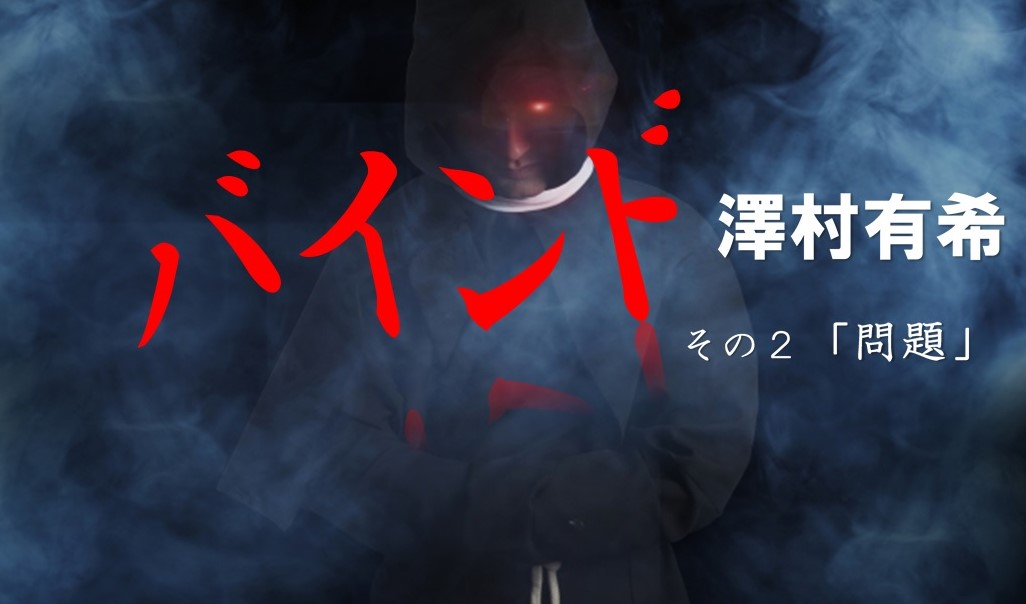「バインド 」澤村有希 その3 ~激励~
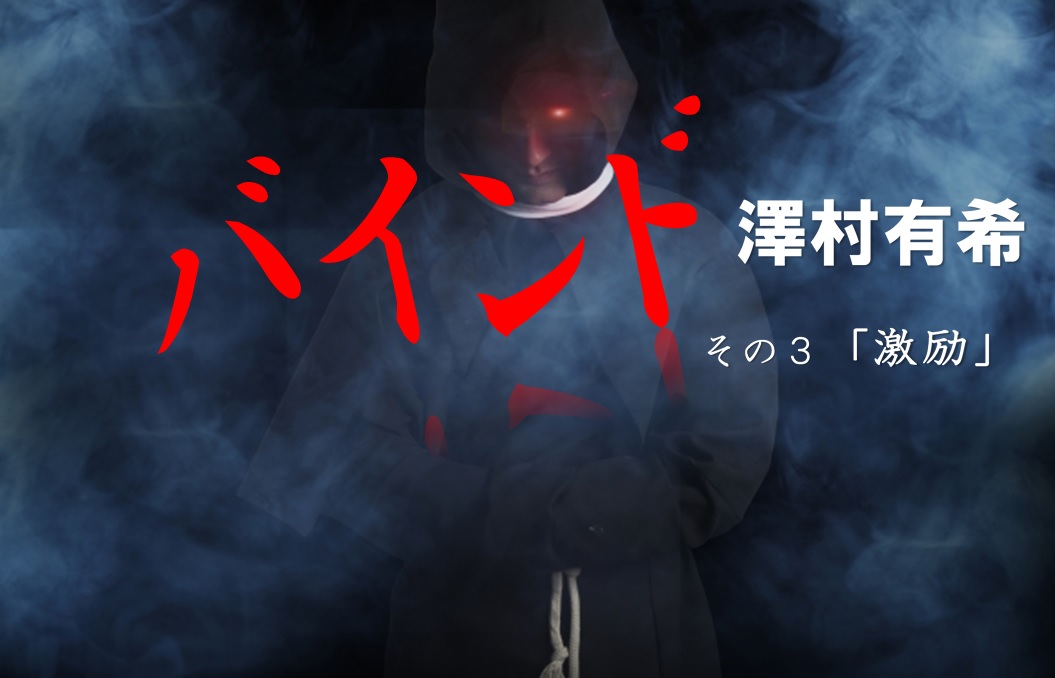
――――結婚を機に、地方都市にある夫の実家で専業主婦をすることになった駒田さん。
嫁ぎ先での初めての夜、奇妙な声音と気配が駒田さんを襲う。
やがて始まる義親の異常な干渉……この家にはいったい何が???―――――
私――澤村の顔を見詰めていた駒田さんは、ふと微笑む。
「亡くなった兄とはある程度の距離はありましたよ。二つ違いで異性の兄妹なので」
でも、もしあのとき兄が生きていたら、と考えたことはあった、と彼女は述懐した。
誰の助けも、解決策もないまま、夫の実家との確執は深まっていく。
遂に、経済的な締め付けも始まった。
夫の給料管理は義父母の手に渡り、妻である彼女の手元には入らない。
生活に必要な物は配達されるか、義母が買ってくる。
服や下着は持ってきたものだけになり、新しいアイテムは一切増えない。髪も伸び放題で、カラーなども出来なかった。
鏡を覗けば実年齢よりも老けた自分がそこに居る。
表情は強ばっており、引き攣っているようにすら見えた。髪にはこれまで一本もなかった白髪が目立っている。すでに隠せるものではなくなっていた。
ついには口座も空になり、携帯もストップ。
外界との連絡手段は夫実家の家電話だけになったが、使おうとすると義母がやって来て止められる。四六時中監視されているようだ。
この頃、彼女は夫の実家でおかしなものを見るようになっていた。
それは、居もしない人間だった。
老若男女が家の中を我が物顔で闊歩している。
どれも普通の外見で、駅前ですれ違う人々のような印象だ。誰ひとり見覚えがない。
彼らは突然目の前に現れ、するりとすれ違っていく。
異様な光景に声を上げると義母の叱責が飛んできた。
「でも、そこに沢山の人が」
「誰も居ない。ああ、うちの嫁は頭がおかしかったのか」
大きな溜め息を吐かれる。これで自分だけに見えていることが自覚できた。
(あんまりな暮らしに、私は頭がおかしくなったんだ)
家事に追われる最中、幻の人間たちに遭遇しても驚かなくなった。
そればかりか、時間さえあれば細かい部分まで観察する余裕が出来た。
(あ。この人、可愛いコート着ているな)
(この髪型、似合わないな)
(アウターのデザインのせいかな、着ぶくれて見えるな)
(暖かそうなブーツだけど、機能面にこだわりすぎて可愛くない)
何度も何度もチェックする内、あることに気づく。
出てくる人たちは全員冬服で、土足のまま家の中を歩いていることに。
愉快だった。この家の中を、靴のまま傍若無人に歩き回る正体不明の存在が、とても滑稽なことに思えたからだ。
我慢できず声を立てて笑っていると、義父母が気味の悪いものを見る目を向けた。
それでもよかった。自分だけに見える世界は、彼らには分からないのだから、と。
夫実家の生活に何も感じなくなった頃、幻の人々の中に変わった二人見つけた。
ひとりは家の決まった場所に現れる。
着ている物と体型から男性だと思うのだが、確信が持てない。
何故なら、顔が隠されているからだ。
これも理由が分からないのだが、番号入りのゼッケンが顔に張り付いているのである。
十六番 ○○学園高等部
名前から考えると、この近くにある私立校である。
男性の右手には特撮の怪獣人形が握られていた。左手には黄色い陸上のバトンだ。
彼が居るのはいつも義父の部屋の前だった。
もうひとりは女性、だと思う。
顔面から後頭部までの白い布で巻いているので、同じく顔が分からない。
布からはみ出した長い髪は明るめのカラーで先端にパーマが残っていた。それに若いコーディネイトの服だ。若い女性なのだろうか。
右手にハンディの電動あんま機らしいもの。左手には金属製の細い孫の手がある。
彼女は義母の部屋の前に決まって佇んでいた。
この二人が出現する時間は決まっていない。早朝の時もあれば、日中もある。真夜中、漸く家事を終わらせた時のこともあった。
二人の姿を目撃する度、どういうわけか身体が熱くなる。
特に下腹と背骨に沿った背中、頭頂部だ。加えて、とても愉快な気分になる。
大声で笑いながらその辺りをクルクルと回りながら踊り出したいくらいだ。
そこを我慢しながら、彼ら二人の傍を通り抜ける。
意味も無く(頑張ってね)と心の中で激励しながら。
もちろん相手は幻なのだから、何の反応もなかった。
~つづく~
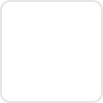

 シェア
シェア ツイート
ツイート