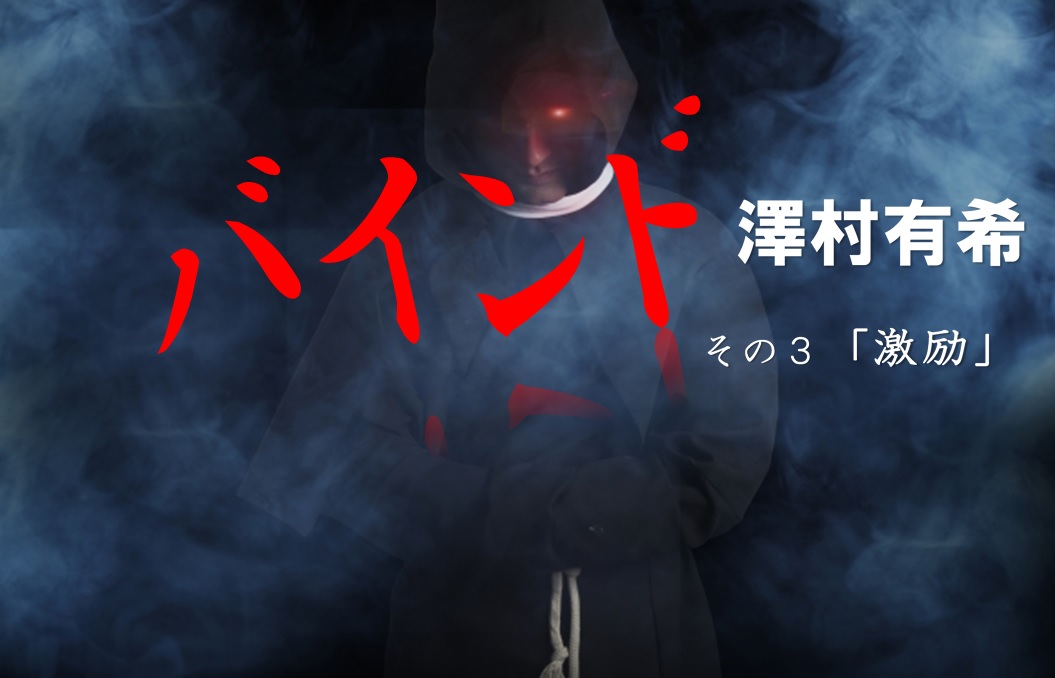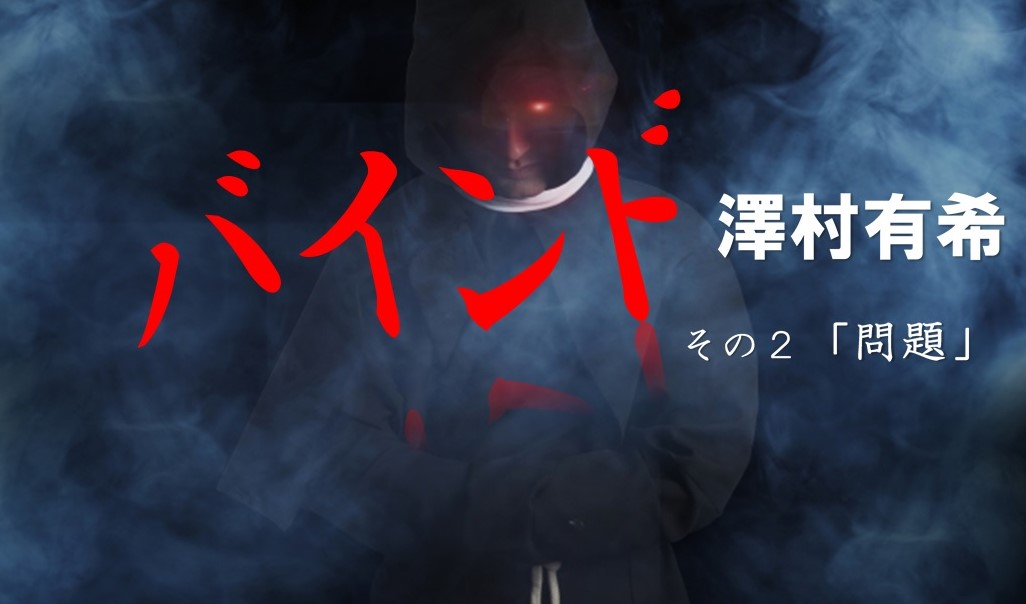「バインド 」澤村有希 その5~存在 ~
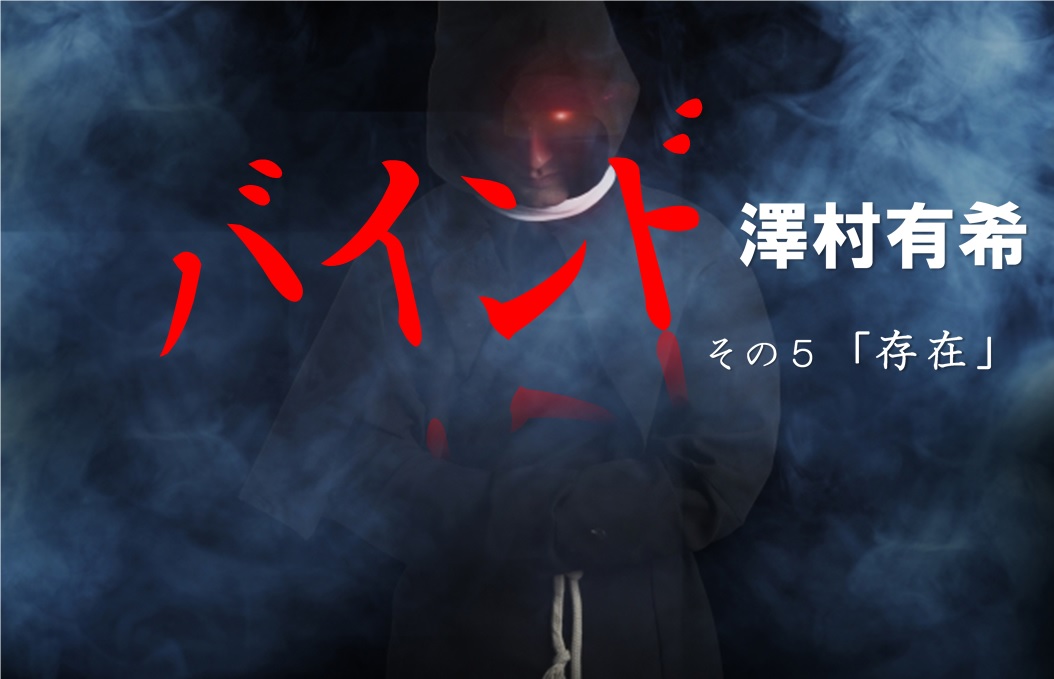
――――義父が長期入院になり、義母も自殺未遂の果てに病院へ。そして、義母の入院を機に彼女の心を熱くさせてきた「幻の人」も消えた。
ついに、彼女は、一人になった――――――。
私――澤村は彼女の夫が戻らないことが気になった。
どこへ行っていたのだろう。会社に泊まりがけだったのか。それとも。
「外にいた女性のところでしょうね。確信しています」
駒田さんは苦笑いで答えた。
誰も――夫すら戻らない家で家事を続け、毎日一汁五菜を整えては棄てる日々。
風呂も焚くが、一番風呂は許されていないなので、帰ってくるかもわからぬのに入ることもできず、いつも水に濡らしたタオルで身体を拭いた。
ある日、戻ってきたばかりの夫が開口一番、こんな言葉を告げる。
「離婚だ。離婚。お前よりいい女がいるから」
記入済みの離婚届を渡され、目の前で自分の欄を書かされる。チェックした夫は「明日役所へ持っていって出しておけ」と命令し、また出て行った。
言うとおり翌日役所へ行こうとしたが、移動手段がない。
歩いていって、窓口へ提出し、離婚が成立した。
だが、家を出て行っていいのか分からない。いつものように家事をこなしておかないと、義父母や夫になんと言われるか。
ひとりで家事をこなして過ごす中、ふと鏡の中の自分の顔をまじまじと見詰めた。
口が動いていた。
自分ではそんなことをしている意識はない。
勝手に言葉が漏れ出している。
〈もう とうきょうへ もどりなよ〉
知らない声が耳に届く。ハッと我に返った。
ああ、そうだ。この隙に帰ってしまえばいいんだ。こんな家、出てしまえばいいんだ。
自分は自由だと初めて気づいた。ふいに気力が湧いてくる。
自分の荷物を纏め、家捜しをして少し纏まったお金を見つける。慰謝料代わりだとその金銭を手にし、外へ飛び出した。
駅。空港。飛行機。久しぶりの東京でビジネスホテルに入って、漸く人心地が付いた。
「それ以来、私の実家にも、あっちの家にも行っていません」
駒込さんは微笑んだ。
彼女は乾家から手に入れた金銭で再就職の準備をし、今は販売業に勤めている。
「怖いのは連れ戻されること。あと、あのとき持ち出したお金のことです。もし、訴えられることがあれば、洗いざらい白日の下に晒して、戦いますけれど……でも、やはり気分的によくないですね」
一転、顔が曇る。
「今、元夫が好きだったものとか、元義父母を思い出す物を見ると、もの凄く厭な気持ちになるんです。なんて言うのかな? 嫌いな虫とか
話の途中で、彼女の携帯にメールが届いた。
改めて訊ねれば、携帯は全て新規に契約をした物で、本当に仲のよい人間や問題ない相手にのみ番号とアドレスなどを教えているようだ。
自身の実家には戻っていないから、あちらは連絡先も知らない。
「あの頃、きっと私の精神はおかしくなっていて、変なものを見たんだと思います。だから、この話は澤村さんが書くような物じゃないと思うんですよね」
そうだろうか。あの「我が家には家族以外の誰かが居る。ひとりだと思う」という元義母の言葉は何を表していたのか。
「……ほら、あの人も、食事を摂らなくなっていた時期ですから。まともじゃなかったんですよ。きっと」
彼女の目が泳いでいる。もう少し細かい部分を質問し、メモに書き留めていった。
ある程度全貌が見えてきたとき、やはり気になるのは〈あちらの家〉のことだ。
その後、何の問題もなかったのだろうか。
「あっちの家からは何も。元夫からメールや電話が来ます。相手の動向が分からないのは怖いので、着信拒否はしていません。途中で切るか、返信をしないといいんです……。
でも、誰が教えたんでしょうね。東京にいる私の知人や友人の一部を彼は知っていたから、そのルートかなと思うのですが、教えるような人間はいないはずですし」
首を捻りながら、あ、と声を上げた。
「これ、まだ話していませんよね?」
彼女の顔が曇る。スマートフォンを取り出し、何度かタップした。
「あの……元夫からのメールにこんな物が」
こちらへ向けられた画面には、メールが映し出されている。
おかしな文面だった。
『おい お前が居なくなったら 父さんがおかしくなったぞ 母さんは死んだ』
日付は二ヶ月ほど前。詳細は書いていない。
彼女は再び何度か操作をし、またメールを見せてくれた。
『おい お前が居なくなったら
つい最近の日付だった。しかし、出る? 戻ってきた、の間違いではないのか? それに、死んだはずの母さんがとは一体? 疑問しかない。
私の心中を察したのか、彼女は抑え気味の声でそっと話し出す。
「出る、って普通、死んだ人が、ってときに使いますよね? 元義母に関してなら、問題ない表現です。でも、元夫のお兄さんって……。亡くなっていたとかそんな話聞いていません。元々戻ってきたら、家を継ぐ継がない、っていう話だってしていたんですし」
そこまで話し、また彼女は押し黙った。
頭の中で何かを整理しているのか、それとも違うのか。
僅かに長い沈黙の後、彼女が私の顔を見据え、口を開いた。
「きっと、元夫が私から返信が欲しいから、こんなメールを送って来ているんですよ。気になるような言い回しの。ね。きっと。そうですよね?」
そうかも知れないですね、と私は答えた。
取材から数ヶ月後、この原稿を書く許可を得るため、駒田さんにメールを送った。
書くことに問題はないと答えが戻ってきたが、その中に気になる一節があった。
『最近、元夫が東京に来ているみたいで、何故か私の最寄り駅周辺を歩いています』
どこから情報を得ているのだろう。心配になり、彼女に電話を掛けた。
『大丈夫だと思います。あっちには見つかっていません。対策していますから』
場合によっては警察や、しかるべき手段に問うべきだと言えば、少し口ごもった。
そして、ポツリと漏らす。
『あの、その元夫の背後に、高校時代の私の兄そっくりな人がベッタリくっついているのを、見てしまって……いや、そっくりと言うより、そのままです。それに元夫はその存在に気づいていない様子なんですよね』
少し間を置いて、彼女が声を潜めて、言った。
――私、また、おかしくなったのでしょうか?
(「バインド」・完)
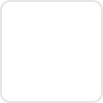

 シェア
シェア ツイート
ツイート