「片町酔いどれ怪談 」営業のK 第5回 ~行きつけの店と常連客~

片町で酒を愉しむようになったのは、俺が22歳の頃に遡る。
きっかけは社会人1年生の頃、会社の先輩が片町のバーに連れてきてくれたのが始まりだった。
「これから社会人としてやっていくうえで、自分の好きな酒を見つけておくのは仕事と同じくらい大切な事だぞ」
「苦しい時や悲しい時に、きっとお前の助けになってくれるはずだから」
そう言って片町のバーを何軒もはしごし、連れ回ってくれた。
当時、実のところ俺は酒に対して嫌悪感に近いものを抱いていた。
だからせっかくのアドバイスもあまり心に響かないというか、ありがた迷惑とすら思っていた節がある。
結局、何軒ものバーを回った挙句、飲んでみた時になんとなく気持ちが落ち着くかな、という理由だけで俺はバーボンを〈自分の酒〉に選んだ。
ウイスキーの知識も無く、特に感動した味だった訳でもない。
どちらかと言うと、早くその場から解放されたい……そんな気持ちが強かったように思う。
しかし、不思議なもので、何となくその時決めたバーボンを今でも俺は愛飲している。
そして長いサラリーマン生活の中でそのウイスキーに助けられた事も1度や2度ではなかった。
先輩とは、俺が転職してしまってからは1度も会っていなかったのだが、人づてに病気で亡くなられたとのちに聞いた。残念ながら、亡くなられてから数年後の事だった。
できることなら、お互いに歳をとった状態でもう1度あの時のバーに行きたかった。
あの時、先輩と一緒に決めたウイスキーを飲みながら、
先輩、この酒、今でも飲んでますよ。
そして、何度も助けられました……。
あの時は本当にありがとうございました!
―――と、心から礼を言いたかった。
遅すぎた願いではあるが。
そんな訳で、今となってはその先輩から〈片町のバーで飲む〉というスタイルを教えてもらった事に大変感謝しているのだが、一方で、バーという空間はその雰囲気のせいか奇妙な事、不思議な事がよく起きるということも知った。
今の俺が書く怪談の根幹にある「霊は決して恐ろしいモノばかりではない」という考え方もバーでの経験からくるものが多い。
もちろんこの連載の1話目に書いたような恐ろしい話も稀に聞く。だが、俺自身が体験した話に限って言えば、バーでの怪に「怖い」という要素はさほど存在しない。
以前、自身のブログにも書いたのだが、俺がよく行くバーでも不思議な事は起こる。
例えばこんな話だ――。
その老紳士は、俺が最初にその店を訪れた時から、ひとりでカウンターに座っていた。
何処か気品があり、彼の周りではゆったりと時が流れている。
静かに酒を楽しむ姿に、
俺も歳をとったらあんな風にひとりで飲んでいたいな……。
そう思ったものだ。
その店が気に入った俺は、それから何度も店に足を運ぶようになったが、いつ訪れてもその老紳士はカウンターの定席にいて、静かにグラスを傾けていた。
一度、マスターにその老紳士が飲んでいる酒は何かと尋ねた事があった。
マスターはウイスキーがずらりと並ぶ棚の奥から1本のウイスキーを大事そうに取り出して見せてくれた。
「これですね……ロイヤルハウスホールド……」
俺はそれを聞き、なるほどあの老紳士に似つかわしいウイスキーだと心の底から納得した。
ただ、
「俺もそのウイスキーを飲んでみたいんだけど」
と言うと、マスターは申し訳なさそうに頭を下げた。
「すみません……この酒は特別な意味があるものですから……」
そう言われてしまい、結局そのウイスキーを飲ませてもらう事は叶わなかった。
少し不思議に感じたが、それ以上突っ込むのは俺のルールに反していた。
だから、きっと何か事情があるんだろうな……と無理やり自分を納得させた。
老紳士は、いつもカウンターの一番奥の席に座っている。
少し目を細めた優しい笑みを浮かべて。
なにか遠い思い出に浸るかのような表情で、ゆったりとグラスを口に運ぶ。
店がお客さんで混み合っている時も、けしてその柔らかな笑みを絶やすことはない。
そうしてひとり静かに酒を楽しみ、やがて他の客に席を譲るようにそっとお店から出て行くのだ。
奇妙なことに、そうやって席が空いた後も決してマスターはその席に他の客を座らせる事はしなかった。
何故?と尋ねても、マスターは笑いながら、
「あの席はあの方の専用席と決めてますから……」
と返すだけだった。

そのうち足繁くその店に通うようになった俺は、不可解な事に気が付いた。
どうやらその店に来る客の大半はその老紳士の姿が見えていないらしいのだ。
一部の常連客はその老紳士に会釈をしたり手を振ったりしているのだが、それ以外の客は、まるでその席に誰も座っていないかのように振る舞っている。
俺は思い切ってマスターに聞いてみた。
「あのさ、マスター……あのお客さんってもしかして?」と。
すると、マスターは、
「Kさんは視える人でしょ? まあ、そういうことですね……」
と笑って頷いた。
それを聞いた時、俺は、どうして自分がこの店に惹かれ、こんなにも気に入っているのかを理解した。
あの老紳士がいるから……その存在のお蔭で、この店独特の雰囲気や気品が保たれているからなのだ、と。
ある時、老紳士がいつものように満席の店内からふらっと出て行った際、マスターがこんな話を聞かせてくれた。
この店をオープンした頃はお客さんも来なくて、毎日閑古鳥が鳴いてました。
まあ、私も決して話し上手ではないですし、愛想が良い方でもありませんからね。
それにお酒だけを味わいに来るバーという場所には、何かプラスαの魅力が無いといけない、というのは分かってたんです。
ただ何を試しても効果も無くて……。
そんな時期が3年ほど続いて、もうそろそろ潮時か……と思っていた時に、あの年配のお客さんがいらっしゃいました。
何も言わずにカウンターの一番奥の席に座って、
『ロイヤルハウスホールドは置いてありますか?
出来ればストレートで飲ませて頂きたいんですが……』
と聞いて来られたんです。
偶然、そのお酒は置いてあったので、すぐにそれをお出しして……。
それを毎日3杯だけ飲んで帰られるんです。
あの日からずっと。毎日。
そのうち私も、あの方が生きている方ではないな、と気付いたんですが、来られるのが怖いとか嫌だとかは一度も感じませんでした。
それよりも、その方と同じ空間にいる。
私がお出ししたお酒を幸せそうに飲んでいる。
それがもう、私にとっても至福の時間になっていたんです……。
それからはロイヤルハウスホールドが無くなりそうになると真っ先に仕入れるようになって。
あの方がお飲みになられているのを静かに見ているだけでバーテンダー冥利に尽きるんですよ……うまく説明できませんけど……。
そのうち、店にも変化がありました。
あの方が来てくれるようになってから、明らかにお客さんの数が激増したんです。
やはり、バーという場所には皆さん、安らぎのような物を求めてくるんでしょうか。
あの方がいると店の空気が優しくなる。
見えない方にも、それは伝わるんですよね。
それからは、どんどんお客さんが増えていって……。
ありがたいことですが、やっぱり私にとってあの方は特別で、今でも一番大切なお客様なんです。
だから、あの席には誰も座らせないし、ロイヤルハウスホールドも他のお客様には絶対にお出ししません。
おかしいでしょ?
あの方が私に話しかけてくれたのは最初に来た時の言葉だけなんですけどね。
それからはいつもニコニコと笑っているだけで……。
そう言ってマスターは嬉しそうに笑った。
そして、その話を聞けた俺もまた……幸せな気持ちになれた。
最近では、俺が店に行くと、その老紳士は軽く会釈までしてくれるようになった。
俺も軽く会釈して挨拶するのだが、その度に俺もまた幸せな気分になる。
俺にとってそのバーは、今ではかけがえのない大切な場所になっている。
このコロナウイルスが収束したら、俺はまた週末には片町へと飲みに出るのだろう。
あの老紳士にも会いたいし、ひょっとしたら。
俺にバーの楽しみ方を教えてくれたあの先輩にも……
いつかまた片町の片隅で会えるような気がして仕方がないのだから。
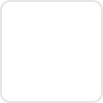

 シェア
シェア ツイート
ツイート



