■「予兆」とは
物事が起ころうとする、きざし。前ぶれ。
■「予兆」はどこが怖いのか
・それが予兆だと分からないまま、厄災が起きてから予兆だったと分かるパターンが多い
・怪談話としては、奇妙な予兆の時点で「ええ!」と驚き、オチでさらに「えええ!」と驚く、つるべ落としのような展開。
・「もしかして予兆なのかも」と気になり出したら、実生活もままならないほどになる。
■「予兆」の反語
・結果
■豊富な「予兆」の世界
『「十歳くらいの頃、その銭湯へ行ったときのことですが、髪を洗っていたら、足もとの排水溝を肌色をした指が流れてきました。血はついていなくて、とても細い、綺麗な指でした。小指だったと思います。驚いてワッと叫んだんですけど、指はするすると流れていって、見失ってしまいました」』
(川奈まり子著『実話奇譚 呪情』収載「私の小指」より)
いきなりインパクトのある引用文である。川奈さんの「呪情」は不気味さ怖さ目白押しの一冊。
中でも「私の小指」はまさしく「予兆モノ」で、文中にそっと置かれる「暗渠」というフレーズに味わいがある、なんとも仄暗い掌編だ。
引用部分の通り、体験者の女性は銭湯内で、排水溝を流れる小指を見る。そして、大人になってから事故で自身の小指を失うことになる。
もし皆さんが排水溝を流れる指を見た時に、これが先の予兆になると思えるだろうか? そうそう「ああ、お風呂で小指を見たから小指の怪我に気を付けよう」とは思えるものではない。
※
『Eさんの頭のなかに突然、あるビジョンが鮮やかに浮かんだ。俄に総毛立ち、そうなるといくら飯が美味くても箸を進めることができない。』
(丸山政也著『奇譚百物語 獄門』収載「九 食堂」より)
こちらは食堂での「予兆」。頭にビシッとビジョンが入ってくる「虫の知らせ」の最強バージョンだ。超能力を感じさせるエピソードにも思える。「食堂」もビジョンの通り、きっちりと良くないことが起きる談話だ。
こうやって「私の小指」と「食堂」を並べて引用すると、予兆の解釈にバリエーションが出て興味深い。
何かが予兆を見せているのか、それとも第六感が働いて自力で見ているのか、なんとも怪しき楽しさがある。
ちなみに丸山政也さんの切れ味鋭い掌編実話怪談は酷い体験談が多く、ガチ怖系怪談ジャンキーにはたまらないものばかりです。記事のネタ探しのために読んでて胸が重くなりました。
※
『そんなとき三国さんは、兄が首を吊る夢を見た。』
(西浦和也著『現代百物語 忌ム話』収載「第二十五話 兄の店」より)
これまた物騒な予兆である。
夢は誰でもみる。「正夢」も身近な予兆の一つで、生まれてから死ぬまでの間に、「その夢は正夢だったんだよ」というセリフを言える人は割合少なくはないのではないだろうか。
ベテラン西浦和也さんの『現代百物語 忌ム話』は一捻りも二捻りもある実話怪談掌編集。引用した「兄の店」も読み終えたときに「おおおお」と声が出てしまうだろう。
■「予兆」は身近な恐怖
と、このように怪談における「予兆」はインパクトのあるものが多いわけだが、非怪談、ごくごく現実的な生活の中でも大なり小なり「あ、なんかそんな気がするな」という思いつきが実際に当たることが往々にしてある。
合理的な理由もなく、「そんな気がする→当たった」の流れは「虫の知らせ」という親しみやすいフレーズが日常的に使われるほど珍しくはないことだ。
故に実話怪談の「予兆モノ」は恐いのだ。
時代劇では草履の鼻緒が切れる。
身近な親戚が入院中の折、家の呼び鈴が鳴ったが玄関を開けると誰もいない。
合理的に考えれば、鼻緒は消耗品だし、呼び鈴は悪戯だ。
だが、人はここに予兆を見出す。
不安が予兆を呼ぶ。
実話怪談マエストロ達が紹介するほどパンチが効いた予兆は稀とはいえ、気になり出せばキリがないほど身の回りは予兆に溢れているのである。
■「予兆」映画から学ぶ
「ファイナル・デスティネーション」というホラー映画がある。2000年にアメリカで公開されたホラー映画で、
飛行機事故を予知して回避した若者グループが死神に追われ、さまざまなヴァリエーションの事故死を遂げる様子を描いたものだ。
冒頭、主人公とその友人が事故が逃れるきっかけとなったのが予兆。主人公が見たリアルな夢そのままに進む現実を恐れ、飛行機に乗るのを止めたことから物語は進む。
この映画はとにかく人がバンバンと景気良く死ぬのだが、死ぬ前に「これから死にますよフラグ」が立ちがちだ。
このフラグは観客にしか分からない場合もあれば、登場人物が察知して死を回避したりもする。
不吉な数字「666」や飛行機事故で亡くなった歌手ジョン・デンバーの歌など予兆が散りばめられ、何度も死にかけた主人公は終盤でもはや被害妄想のレベルまで意識を拡張して予兆を察知。目に入った錆びた釘を見ては「破傷風にする気だな!」と周囲に誰も居ないのに、がっつり声に出して息巻くほどになる。
実話怪談の場合は「予兆→結果」までがワンセットとして提示されるが、日常生活の中でガチで予兆に怯え始めたら、実際にこうなるだろう。まだ何も起きていない、でもこの目の前に起きた何かが予兆だったら恐い。
こんな恐怖が成り立つのだ。
ここに「起こりうることは起きる」でお馴染みのマーフィーの法則が働くと、実話怪談の出来上がりだ。
ヒットした「ファイナル・デスティネーション」は5作の続編があり、シリーズを重ねるごとにその予兆描写も露骨になっていくので、見終わったあとについつい身の回りの予兆を探したくなるナイスな映画だ。「起こりうることは起きる」と思いながら、辺りをキョロキョロして怯えるのも一興だ。
もし、あなたの周りに何か普段と違うことが起きてそこにピンとくるものがあったら、まずは予兆を疑ってほしい。
第六感であれ、霊的なものであれ、それはそれで楽しい世界観だと私は思う。
書いた人
玉川哲也(たまかわ・てつや)
オカルトをこよなく愛でる新進気鋭のフリーライター
カテゴリ——怪語事典

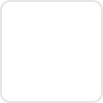





 シェア
シェア ツイート
ツイート



