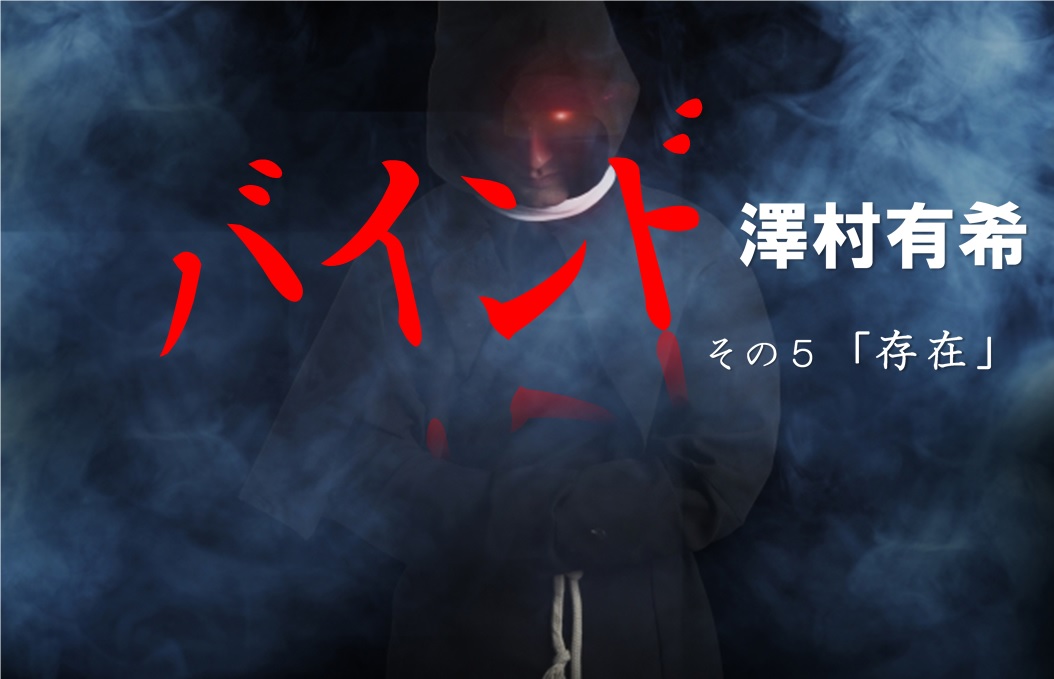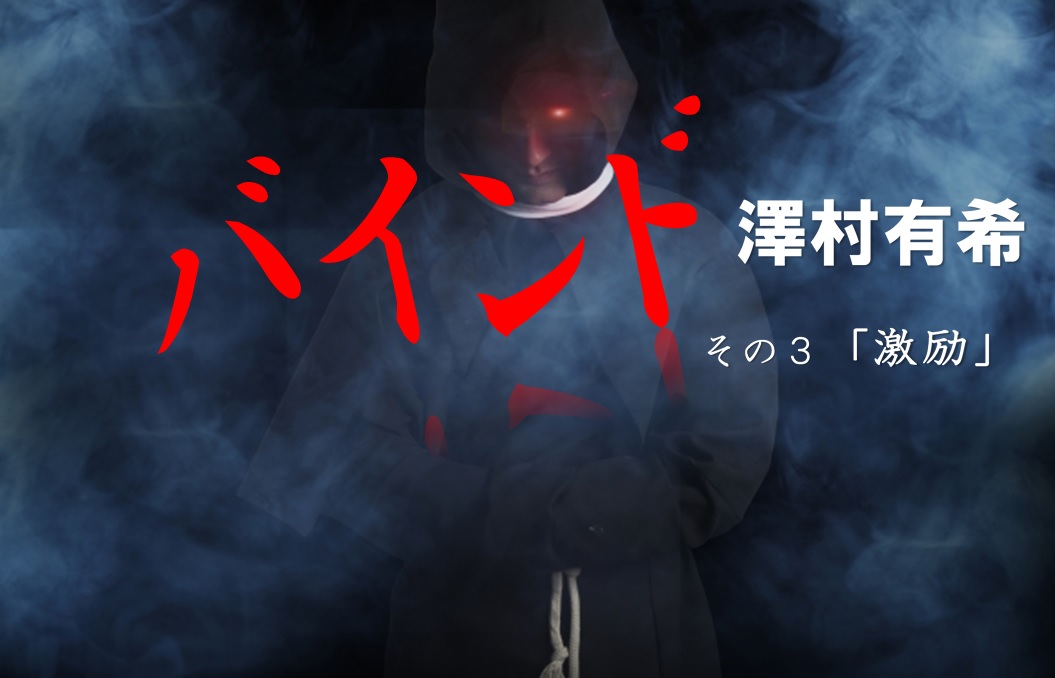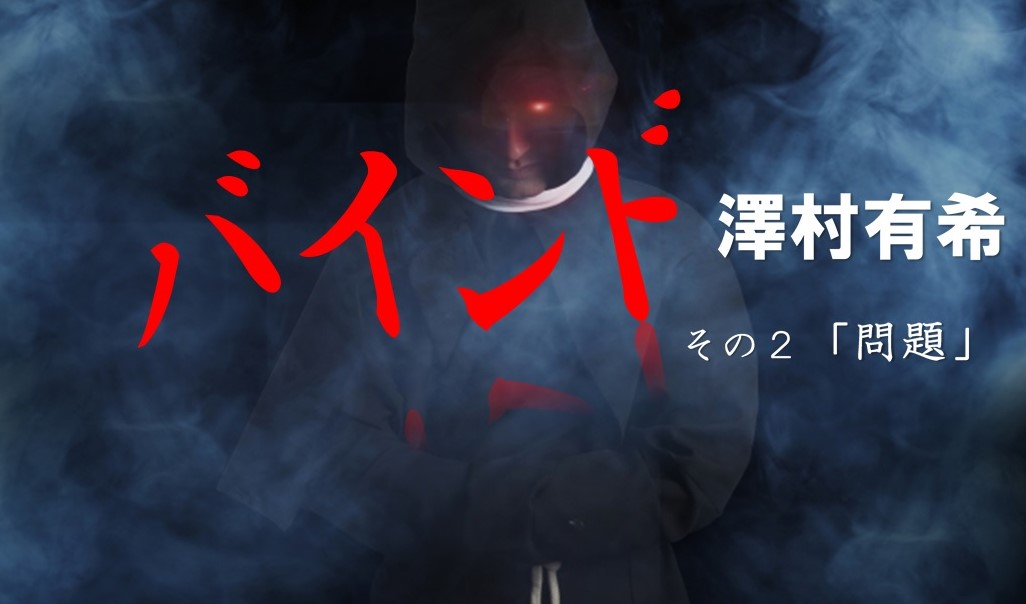「バインド 」澤村有希 その4 ~閑散~

――――家の中に現れる幻の人影たち。その中でも異質な二人の男女。義父母の部屋の前に立つ彼らを見ると、駒田さんは無性に気分が高揚し、激励したい気分になるというのだが……
私――澤村が訊く前に、駒田さんが教えてくれる。
「その二人に出会ったとき、楽しくなったり、頑張ってねって言いたくなったり、って、本当に自分でも分からない気持ちでしたよ。本当に、分からない」
でも、と彼女は暗い口調で続けた。
あの二人の存在に気づいてから間もなくして、義父が入院となった。
帰宅の途中、玄関の前で転倒し、そのまま立てなくなったのだ。
義母が付き添い救急車で運ばれていったが、そのまま手術となった。身の回りの世話をさせられるのだろうと準備をする。
その数時間後、義母が激怒しながら戻ってきた。
「お父さんの世話はしなくていい。世話する女が来ているから」
それだけ言うと、部屋に閉じこもる。前から喧嘩の種になっていた愛人が来ていたようだ。すでに夜中だが、食事などは要らないのだろうかと気を回すが、何も言われない。
いつの間にかあの〈白い布で顔を隠した女性〉が義母の部屋の前に立っていた。
いつもと違い、両手を部屋のドアへ向けて差し出している。
マッサージ器と孫の手は握ったままだったからか、何かおかしな儀式に見えた。
部屋に戻ると、いつの間にか夫がベッドに潜り込んでいる。
鼻の下まで掛け布団に埋まり、目だけがこちらを向いていた。
知らない匂いが漂っていた。
香水なのか、それとも衣服の洗剤臭なのか、それともコンディショナーやボディソープなのか。
ボォオーッ、ボォオーッ、ボォオーッ、ボォオーッ。
不意におかしな音が響いた。脳裏にイメージが浮かぶ。複数人の男たちが口を卵形に開いて――すぐに思い出した。結婚の挨拶の時聞いたものだ。
今回はすぐ傍で鳴っている。多分、夫の方から。
彼の目が嗤っていた。こちらを見ていないのに、それが良く理解出来た。
ボォオーッ、ボォオーッ、ボォオーッ、ボォオーッ……。
夫を放置し、廊下へ出た。キッチンへ入り、冷たい床の上で跪いたまま一夜を明かした。
もう部屋へは戻れなかった。
義父は長期入院になったと聞いた。
そのせいで更に忙しくなったと夫は家に戻ってこない。
義母と二人の生活になったも同然だった。
ところが以前より過ごしやすい。何故かと考えれば、義母と顔を合わせることが減ったからだ。三度の食事は朝夕の二回となったほどだ。
とはいえ、家事は完璧にこなしておく。
毎日、義母のために高麗鼠のように働いた。
その甲斐あってか、まれに褒められることがあった。特に夕食の時間が多かったように思う。しかし箸が進んでいない。三分の一も食べぬ内、義母は自室へ戻った。
余った料理は廃棄する。いつもよりゴミが増えた。
食べないのに、義母は痩せなかった。血色もよい。
代わりに、ではないが、時折「我が家には家族以外の誰かが居る。ひとりだと思う」と口走るようになった。
そんなときは決まって四方を確認するように目をグルグルと動かす。
いつもの顔と違って、何かに怯えているような表情だ。
確かに家の中には自分にしか見えない何かが出現しているが、ひとりではない。複数だ。それに他と違うのも男性と女性の二人だから数が合わない。
(こんなことを言ったらよくない)
義母には気のせいでしょうと、お追従を言って誤魔化した。
しかし、後日――雨が雪に変わりそうな日だった。
義母が自室のドアノブで首を吊っているのを発見してしまった。
見つけたタイミングがよかったのか一命を取り留めたが、その後は病院に入り、家に戻ってくることがなくなった。
夫は仕事に邁進し、自分の両親がこんなことになっているのに戻ってこない。
ガランとした家の中で、あの幻の人々に囲まれて過ごす他なかった。
が、義父母が居なくなってから、あの二人の姿を見ることはなくなったように思う。
思い返してみれば、男性の方が先で、義父が入院してから。
女性は義母が居なくなってからだと思う。
だから、彼女はとても寂しい気分になった。
例え相手が正体不明の存在でも心の支えになっていた、のかも知れない。
後に考えると、とてもおかしなことだったのだが――。
~つづく~
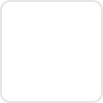

 シェア
シェア ツイート
ツイート