「片町酔いどれ怪談 」営業のK 第8回 ~客が来ない理由~

片町には俺の行きつけのスナックが何軒かある。
その中でも特に行きつけになっている店がある。
セット料金3000円で、ボトルを新たに入れたりしない限りは、閉店まで飲んでいても、3000円ポッキリという安さである。
常連さんも個性豊かな人達ばかりで、何回通っても飽きる事がない。
そして、何よりも嬉しいのは、その店に行くと勝手に怖い体験談が聞ける――という事である。
そんな店だから、コロナ禍になる前は毎週のように顔を出していた。
その日も俺は、週末の土曜日に、片町へと出掛けた。
これまた行きつけの串カツ屋でお腹を満たした後、そそくさとその店に向かう。
勢い良くお店のドアを開け、
「こんばんは~!」
と言うが、お店のママさんと従業員のお姉さんは、何やら浮かぬ顔をしていた。
それでも、俺に気付くと、
「あらあら!」
と対応してくれたが、やはり顔が暗い。
「どうかしたの?」
と聞くと、ママさんは機嫌の悪そうな顔で、「今週は何故かお客さんが1人も来ないのよ!」と話してくれた。
「ということは……もしかして俺が今週最初の客?」
と聞くと、
「そうなのよ」
と吐き捨てるように返してきた。
確かに、「いつも満席」とまでは言わないが、少なくとも2~3人は常に客がいて、上機嫌でカラオケを歌っているのがいつもの見慣れた風景だった。
それなのに、その日は俺以外には誰一人いない。
「不思議な事もあるもんだねぇ」と言うと、ママさんが言い難そうにこう言った。
「実はね。毎年、こういう事が起こるの。それも決まって今頃なんだけどね」
俺は作ってもらった水割りを口にしながら、うんうん、と興味深々で聞き入った。
「昔、この店に来てたお客さんなんだけどね。
Kさんが来るようになる、ずっと前のことなんだけど……。
そのお客さんっていうのが、かなり我侭な方でね、お店で私達が他のお客さんと話してると、それだけで機嫌が悪くなっちゃうの。
だから、お店としてもある意味少し敬遠してたお客さんになるんだけどね……。
まあ、当の本人は敬遠されてたなんて気付いてもいなかったみたいなんだけどね。
で、ある時、他のお客さんが、その人にはっきり言ったのよ。
あんただけの店じゃないんだからもう少し周りに気を遣えよ……って。
それからしばらくはそのお客さんは来なくなったんだけどね。
ある日、お店に電話が掛かってきて……
明日は貸切で飲みたいから、お店空けといてって。
そんなの困ります、っていう間もなく、電話が切れちゃって。
で、翌日、しょうがなく貸切にして、そのお客さんを待ってたんだけど、結局、お店には来なかったの。
で、その後かな。
そのお客さんが、お店に向かう途中に事故で亡くなったって聞いたの。
そんな事があってから、毎年この時期になると、お客さんが寄り付かない日が続くようになっちゃって……。
こんなこと思いたくないけど、もしかしたら、そのお客さんがそうさせてるのかな……なんて思ったり」
そう言われて俺はこう返した。
「もしかして、そのお客さんって、いつも一番右隅に座ってなかった?」
すると、2人の顔が少し引きつるのが分かった。
「どうしてそんな事を知ってるの?
前にもこんな話をした事があったかしら?」
そう言ってからしばらく黙り込んで、
「もしかして、この店に何かいるのが視えてる……とか?」
と泣きそうな顔で聞いてくるママさん達に、俺はつい悪戯心が顔を出してしまう。
さきほど俺が「右端の席」と言ったのは、ママさんがチラッチラッとそちらの方を見ながら話していたのに気付いて、勘で言ってみただけなのだが……。
ただ、お店全体の空気が冷たく重かったのは事実で、照明も心なしかいつもより暗く感じた。
俺は、水割りを一気に飲み干し、更に追い討ちをかけようとした。
その時――。

突然、お店のドアがドンドンと大きな音で叩かれた。
俺達3人は、思わずビクッと肩をこわばらせた。
「……今の何?」
そう聞く俺に、無言で固まるママさん。
すると、再び、ドンドンドンとドアが叩かれる。
石のようになってしまったママさんに代わって、俺が返事する。
「は~い!どうぞ~!」
努めて明るく声を掛けてみるも、ドアが開く気配はなかった。
代わりに、ドアの向こうから低い声が聞こえてくる。
〈ごめん。遅れて……〉
俺はママの顔を見た。
ママさんの顔は更に恐怖で固まっている。
「死んだお客さんの声?」
と尋ねると、黙って頷く。
こんな事に出くわすから、この店に来るのは止められないのである。
俺はその時、心の中でガッツポーズをして歓喜していた。
しかし、そんな心の内はおくびにも出さず、俺はドアに向かって語りかけた。
「あなたは、もう死んでるんですよ?
死んだ人が、こんな所に来ちゃ駄目でしょ?
それとも、一緒に酒でも飲むの?」
できるかぎり優しく、だが強い口調でそう言った。
一旦、水をうった様に店内が静まり返る。
しかし、しばらくすると、再びドアが叩かれだした。
今度は先ほどのような遠慮がちな音ではない。
ただただ怒りに任せたような叩き方で、
ドンドンドンドン……! ドンドンドンドン……!
引っ切りなしにぶつけてくる。
「ママ、塩ある?」
「……アジ塩しかない」
まあ、無いよりましかと思い、渡されたアジ塩を思い切りドアに振りかけた。
すると、ドアを叩く音が少し弱まったように感じた。
だが、その代わりに荒い息づかいがドアの向こうから漏れ聞こえる。
「たぶん、こっちが開けない限り、向こうからは入っては来れないと思うけど……」
安心させようと思ってそう言ったが、ママさんは泣きそうな顔で眉を下げた。
「じゃあ、帰る時はどうすればいいの?
このままずっとお店の中に居られるわけも無いのに……」
……なるほど、もっともな心配である。
そこで、俺はポケットから携帯を取り出すと、同じ片町にある、別の店に電話をかけた。
その間も、ずっとドアを叩く音、唸るような荒い息づかいが聞こえていたのだが……。
そして、電話をしてから10分後、突然、お店のドアが開いた。
「きゃあ!!!」
飛び上がって驚くママさん達。
だが、ドアのところに立っているのは勿論、幽霊なんかではない。
さきほど俺が電話で呼びだした男性がきょとんと立っていた。
呆然とするママさんに、
意味がわからないという顔で立っているその男性。
俺だけが愉快に笑っていた。
実は以前、Aさんと片町に飲みに行った時、教えてもらった事があったのだ。
いいですか、Kさん。
たとえ幽霊といえども、苦手な人間っているんですよ。
だって、もともと人間だったんですから……と。
そして、その時にAさんから、【霊に嫌われるタイプの代表】として太鼓判を押されたのが、その彼だった。
Aさんの見立て通り、先程の男の霊も、彼が苦手だったということだ。
さっきまで感じていた重たい気配も、男の唸り声も、今はもう綺麗さっぱりどこかへ消えてしまっていた。
店の照明も急に明るく感じられる。
その後、彼に水割りをごちそうして、そのまま閉店まで居てもらった。
やれカラオケだ、ロックだと、好き放題頼まれて高くついてしまったが、その後、そのスナックに客が来ない日は無くなったらしい。
著者プロフィール
著者:営業のK
出身:石川県金沢市
職業:会社員(営業職)
趣味:バンド活動とバイクでの一人旅
経歴:高校までを金沢市で過ごし、大学4年間は関西にて過ごす。
幼少期から数多の怪奇現象に遭遇し、そこから現在に至るまでに体験した恐怖事件、及び、周囲で発生した怪奇現象をメモにとり、それを文に綴ることをライフワークとしている。
勤務先のブログに実話怪談を執筆したことがYahoo!ニュースで話題となり、2017年「闇塗怪談」(竹書房)でデビュー。
好きな言葉:「他力本願」「果報は寝て待て」
ブログ:およそ石川県の怖くない話!
★「片町酔いどれ怪談」は隔週金曜日更新です。
次回の更新は7/10(金)を予定しております。どうぞお楽しみに
★営業のK先生最新刊「闇塗怪談 醒メナイ恐怖」明日6/27発売です!
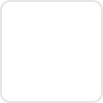

 シェア
シェア ツイート
ツイート



