「片町酔いどれ怪談 」営業のK 第1回 ~其処にいるモノ~

片町には沢山のバーが在る。
これは俺が、行きつけのバーのマスターから聞いた話だ。
彼が修行時代に体験した不思議な話なのだが、これがなんとも好奇心をそそられる話なのだ。
バーという業界もやはり他の飲食店同様、最初は修行のような形で仕事を覚えさせてもらい、その店のマスターから認められて初めて、独立開業となるのだそうだ。
彼は片町にあるバーで修行をしてから、同じ片町の他のバーに移り、再度修行した後に独立開業したそうだ。
それはある意味、バー業界においては仁義に反する行為であり、彼自身も本来ならばずっと最初の店で修行を積みたかったらしい。
だが、それは元々働いていたバーのマスターが自ら勧めたことなのだという。
そして、その店を移った理由というのが、今回書く話になる。
そのバーのマスターは、まだ50代手前という若さであり、頑固だが、酒に対する知識や技術には素晴らしいものがあった。
何より酒に対する愛情が異常とも言えるほどに強かった。
人間的にも立派な人格者であり、将来自分のバーを持ちたい彼にとっては、これ以上の師匠はないと断言できるほどに素晴らしい人、いわば〈バーの達人〉であったという。
ただ、ひとつだけ問題があった。
まだ若かった彼は、一緒に働く仲間たちとたびたび怖い話で盛り上がっていたのだが、その度にマスターから、
「霊の話など絶対にするな!」
と激怒されたのだという。
店の若い者たちはみな、きっとマスターは幽霊なんて信じてないんだろう、だからあそこまで毛嫌いするんだな、と思っていた。
しかし、それは彼らの思い違いであったことが後に判明する……。
実はそのバーの向かいには、マスターが借りている空きスペースが在る。
在るのは知っていたが、誰も入るのを許されたことのない禁忌の場所でもあった。
バー自体はビルの地下にあったそうなのだが、マスターがその店を借りる際、向かいの空きスペースも一緒に借りることが条件だったらしい。昔は店が入っていたようなのだが、当時はもう潰れて久しく、いったいいつ頃からそのスペースが空いたままになっているのかマスターにも分からないのだという。
マスターは店と一緒にそのスペースを借りて以来、ずっと使用せずに放置していた。
だが、そのうちバーの貯蔵庫が一杯になってしまい、何処かで貯蔵スペースを借りなければという話になったとき、さすがに従業員たちも黙っていられず文句を言ったという。
「マスター、せっかく目の前に空きスペースが在るのに、どうして其処を使わずに別の場所を探さなきゃいけないんですか?」
確かに、別の場所に貯蔵庫が出来ると、その場所から重い酒瓶を運んでこなければならず手間がかかる。それならば目の前にあるスペースを有効活用した方が楽じゃないか、と彼らは考えたのだ。
しかし、マスターは頑として首を縦には振らなかった。
これには普段マスターを尊敬し、反抗することもなかった彼らも納得がいかず、半ば意地になってこう言い返した。
「マスターが、どうしても他の場所を借りると言うのでしたら、僕ら、全員でこの店を辞めさせて貰います!」と。
マスターは一瞬驚いた顔をしたが、次の瞬間諦めたように目を伏せると、重い口を開いた。
「……あの場所はな、本当に使ってはいけないんだ。お前たちが霊の話をすると、俺はいつも怒鳴っていたよな? それは俺が幽霊を信じていないからじゃない……。実際にこの眼で、その場所で、本物を視てしまったから怖いだけなんだ。だから、お前たちも実際に見てみるといい……もう霊の話なんて絶対にできなくなるから」
そう言って、古く汚れた鍵を彼らに渡してくれた。
彼らは、マスターに一礼すると、すぐに向かいの空きスペースへと向かった。
皆、本当にその場所に幽霊がいるのなら、自分達の眼で確かめてやろうと意気込んでいた。
ドアは鍵穴が錆び付いており、差し込んでもなかなか開かない。
しかし、力の入れぐあいや角度など試行錯誤を繰り返しているうちに、ガチャっという鈍い音とともにドアの鍵が開いた。
部屋の中に電気が来ている訳もなく、中は真っ暗だ。
彼らは慌てて懐中電灯を取りに行った。
「おい、あったぞ!」
店に1本だけあった懐中電灯を持ってくると、その明かりを頼りに空き部屋の中へと入っていった。

同行した店員は彼を含めて3人。
懐中電灯を手にした彼が先頭に立って進む。
しかし、その店の中は異様だった。
本当にかつて店として営業していたのか疑わしいほどに何も無い。
床は固まった泥で覆われ、どこから生えたのか蔦のような植物があらゆる場所に這いのびていた。
床と同じく、泥を塗りたくったような壁にはいたるところに変色した御札らしき物が無数に貼り付けられている。
(なんなんだ……此処は……?)
彼らはおっかなびっくり少しずつ奥へと歩を進めた。
そして、1枚のガラスで仕切られた場所を照らした瞬間、彼らは愕然とした。
ガラスの向こう側、誰かがその場所に立っていた。
人の形をした何かが……。
(灰色のマネキン……?)
最初はそう思ったという。
とにかく灰色をした何かが鎖に縛られるようにして壁に張り付けられていた。
(なんなんだ?……これは?)
それは彼らがそれまでに見てきたものや聞いてきたものとは明らかに違っていた。
空気が凍りつき、重く圧し掛かってくる。
刹那、耳鳴りと軽い頭痛を感じた。
彼らは訳が分からないまま半ばパニックになっていた。
きっとマネキンに違いない。よく見れば……きちんと確かめれば……怖くない。
そうだ、ほら――。
しかし、彼らが懐中電灯のライトを当てると、それはうっすらと透けて視えた。
(――……!!!)
思わず固まってしまった彼らは、その場から一歩も動けなくなった。
ライトを下ろすことも消すこともできない。
そして次の瞬間、ライトに浮かび上がった灰色の人間は、睨むように両目を開けた。
「----------ッッ」
それを見た彼らは、一気にその場から走って逃げた。
必死の思いでドアから出ると、其処にはマスターが立っていた。
まだ震えている彼らから鍵を受け取ると、
「ちゃんと視えたか? ドアの鍵は俺が閉めておくから……」
そう言って辛そうな顔をしたという。
結局、それが原因で彼らは毎夜何かに魘されるようになった。体調も悪化し、どんどん痩せていく。
全員、ひと月ももたなかった。
状況を見兼ねたマスターは彼らに、こう告げた。
「お前たちはもう此処には居ない方がいい。早く忘れるんだ……もう。そうしないと俺のように……」
そう言って、マスターはその後の言葉を飲み込んだという。
彼ら3人は、もうその店に近づくことすら恐ろしく感じていたから、マスターからの申し出を黙って受け入れた。
その後、彼はすぐに別のバーを探して、心機一転修行に励んだ。
ただ、その3人のうち、バーテンダーとして仕事を続けているのは彼だけであり、他の2人に関しては安否すら分からないのだという。
彼らが辞めてから半年ほどで何故かそのバーも閉店した。
突然の出来事で、彼も驚き、勇気を出してマスターに会いに行ったらしいのだが、結局
マスターとはそれ以降一度も会えていない。
店が入っていたビルは、いまだに残されたままになっている。
ただし、灰色の幽霊が立っていたあの店のドアを完全に塗り固めた状態で、だ。
「其処にドアが在って、中に何かがいるなんて誰も考えないんじゃないかな……」
彼はうすら寒い笑みを浮かべてそう言うと、こつんと俺の前にグラスを置いた。
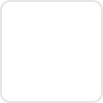

 シェア
シェア ツイート
ツイート



