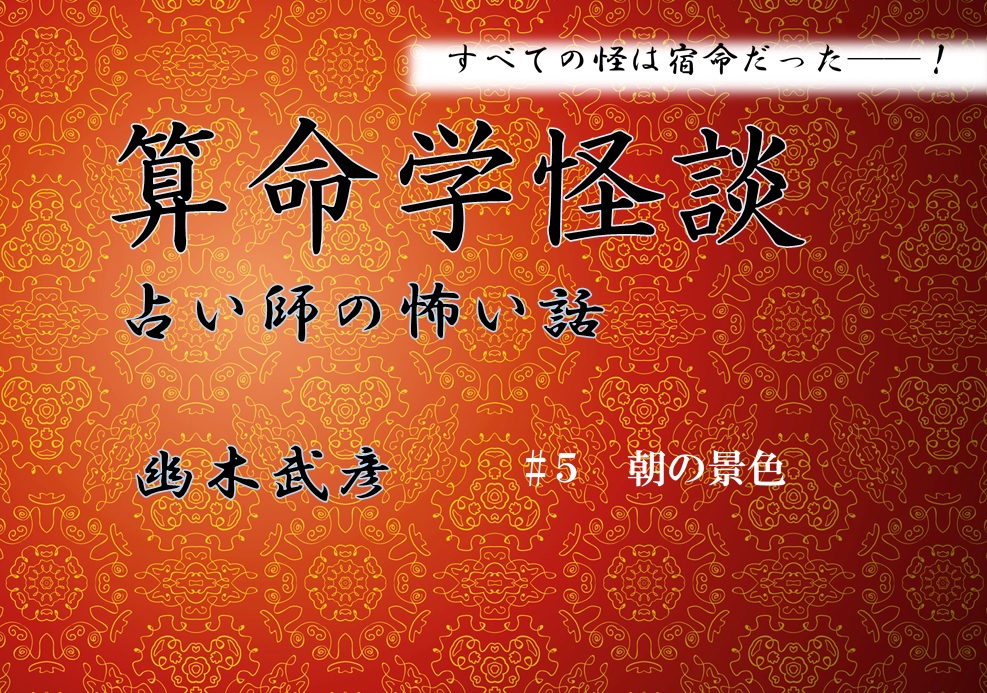異国ロンドンのホテルで起きた恐怖の一夜…「算命学怪談 占い師の怖い話」
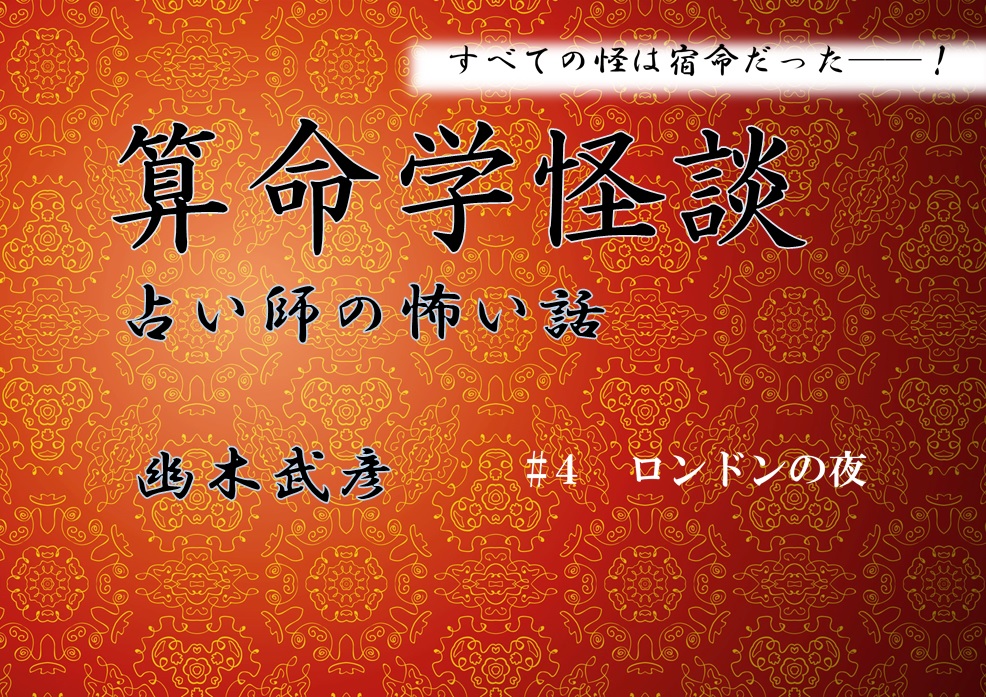
第3回まで「算命学」の命式、人体図に纏わる怪奇事件をお送りしてまいりましたが、ここで閑話休題。
今回は占いを少し離れ、著者の元に寄せられた海外での恐怖体験談をお届けいたします。
目次
#4 ロンドンの夜
欧州某国で暮らす小夜香さんから聞いたエピソード。
「これは、二十年くらい前の話です」
小夜香さんは言った。
「あるツアーに参加した私は、みんなとイギリスを訪れました。ウェールズへの旅だったのですが、最初の一泊はロンドンでした」
小夜香さんが参加したのは、当時彼女が夢中になっていたフラワーエッセンス・セミナーの研修旅行だった。
「今でこそポピュラーになってきましたけど、あの頃はまだフラワーエッセンスはあまり日本では知られていませんでした。そんな状況で第一線に立って広めようとしていたのが、私が学んでいたセミナーの主宰者。ツアーを引率したのもその女性です」
研修旅行の参加者たちは、長時間に及ぶフライトの疲れをとる目的で、ロンドンのホテルに投宿した。
メンバーは総勢十五人ほど。全員女性だったという。
ホテルはテムズ川に架かる豪奢なタワーブリッジのすぐ近くにあった。夜になると、ライトアップされた橋がとても美しかったことをよくおぼえていると、小夜香さんは言う。

「ホテルに到着したのは夕方頃でした。いったん解散し、それぞれの部屋にチェックインをしたら、希望者だけもう一度集まって、川沿いを散策したり、一緒に夕食を取ったりしようということになりました」
小夜香さんはさっそくチェックインをすませ、部屋に入った。
客室はツインルームで、相部屋になったのはそのツアーで初めて知りあったAさんという女性だった。
小夜香さんは同世代らしいAさんと挨拶をかわし、部屋にそれぞれの荷物を置くと、集合のため、二人してロビーに戻った。
だが、思っていたより疲労が激しい。
先ほどまでは、ぜひみんなと一緒にと胸躍らせていたはずなのに、いつしか気分がすぐれなくなっていた。
「Aさんも私と同じような体調でした。お腹が空いているのに食欲もなく、みんなと一緒に出かける気力はすっかりなくなっていました」
長いフライトのせいで、疲れが溜まってしまったのだろう――そう考えた小夜香さんは主宰者の女性に事情を話し、Aさんと二人、部屋に戻って休むことにした。
小夜香さんの記憶では、ホテルは七階建てぐらい。彼女たちが泊まった部屋は、その三階にあった。
客室は、ごくありきたりなビジネスホテルのような作りだった。
入口の脇、入ってすぐ右側にバスルームがある。
そのまま奧に進むと、右にベッド。二つのシングルベッドがベッドヘッドを壁につけ、間隔を空けて並んでいた。
反対側の壁には作りつけの細長いテーブルがあり、テーブルの隅にはテレビが置かれている。
二人は交替でシャワーを浴び、夜着に着替えて床についた。小夜香さんが入口に近い方のベッドで、窓に近い奥のベッドをAさんが使った。
「それからどれぐらい眠ったのか。私はふと、奇妙な気配を感じて目を覚ましました。すると……部屋の中をゴソゴソと、なにかが動いているんです」
小夜香さんは仰向けに横たわっていた。最初は、Aさんが起きたのかと思ったという。だが、何だか様子が変である。
「起き上がろうと思ったのですが身体が動きません。金縛りでした。私、目は開けていなかったと思います。でも、誰かが部屋の中を歩き回っているのが分かりました。なんだかやけにせっぱつまった感じで、何かを探しているように思えました。そして……なぜだかとっても、その人は怒っていました」
小夜香さんは目を閉じて横たわったまま、不気味な気配を追い続けた。
おかしなことに、その何ものかは部屋の中を、まったく同じ動線で、何度も何度も行ったり来たりする。
窓側のベッドを、脇から足もとまで移動した。
そしてベッドに沿ってぐるりとまわり、今度は反対側の縁をベッドヘッドがくっつけられた壁際まで歩いてくる。
再びきびすを返した。小夜香さんのベッドの周囲を回るように動きだす。
いったん足もとまで移動した。ベッドの縁をまわると、またしても枕元まで歩いてくる。
「まるで、Wという文字を書いているかのような動き方でした。そんなわけの分からない行動を、それはもう延々とくり返すんです」
何をしているのと思いながらも、同時に小夜香さんは戦慄にも襲われた。
決して目を開けてはいけない。この人を見てはならない――理由は定かではないもののそう感じ、目を覚ましてしまった自分を怨んだ。
「起きたことに気づかれてはならないと思って、必死に眠ったふりをしました。お願い、どうか気がつかないでと祈りにも似た気持ちで息を殺し、狸寝入りを続けたのです。ところが私、怖さのあまり、だんだん身体が震えだしてしまって」
どうしようと思ったものの、もう遅かった。
さらに数回の、行ったり来たりの後。小夜香さんとAさんのベッドの間。
Wという文字のちょうど真ん中あたりにさしかかったとき、謎の人物は、突然足を止めた。
「私の方を見ていました。じっと見ています。じっとです。私は目を閉じたままでしたが、はっきりとそう分かりました」
どす黒い恐怖の塊が、喉の奧からせりあがってきた。今にもそれは悲鳴へと変わりそうになったという。
「どうしよう。どうしよう。どうしよう。パニックになりながらそう思った、次の瞬間でした」
それは、いきなりベッドによじ上ってきた。
小夜香さんに覆いかぶさる。
とんでもない重さだった。胸を押しつぶされそうになった小夜香さんは、くわっと目を見開いた。
黒い影が、そこにいた。
部屋の中に満ちていた闇など、比べものにもならない黒い影。
影の両手が、小夜香さんに回った。
首を絞める。
小夜香さんはさらに目を剥いた。
首に回った黒い指が、ギリギリと喉に食いこんでくる。
「殺される。そう思いました。私は必死になってもがきました。でも、重くて、苦しくて、怖くって、思うようになりません」
黒い指は、さらに深々と喉に埋まった。
もはや息もできない。
小夜香さんは懸命にもがいた。四肢を暴れさせた。
助けて。
助けて。助けて。助けて。
隣のベッドにいるはずのAさんに叫ぼうとするものの、首を絞められているため声も出せない。
「もう完全にパニックでした。身体がしびれ、頭の中がぼうっとしだしたのが分かります。やだ、やだやだやだ。それは最後の抵抗だったのかもしれません。私は渾身の力をふりしぼって――」
狂ったように腕を動かした。
そのとたん、金縛りがとけて腕があがった。
「勢いあまって、ベッドヘッドに思いきり手を打ちつけました。その痛さとともに、スッと身体が軽くなって。私は弾かれたように飛び起きました」
だが、黒い影は、もうどこにもいなかった。
小夜香さんは肩を上下させて荒い息をつき、しばし呆然とした。
隣のベッドを見ると、Aさんはこちらに背を向け、横臥したまま眠っている。
注意深く、その様子を観察した。だがどう見ても、急いでそこに飛びこんで、狸寝入りをしているようには思えない。
「やっぱり、歩き回っていたのは彼女ではないと確信しました。じゃあさっきのはなに。私は夢を見ていたの? 寝ぼけていたの? でも、ベッドヘッドにぶつけた手首は、まだ生々しい痛みを発したままです」
小夜香さんは、そっとベッドを抜けだした。
バスルームに向かう。
もしかして、誰かがそこにいるかもしれないと思いながら。
「私は、バスルームの前まできました。とくとくと、心臓が拍動を速めます」
ドアノブをつかんだ。ヌルッとノブがすべる。自分が指と手のひらに、いやな汗をかいていたことにようやく気づいた。
今にも叫びだしてしまいそうな恐怖をこらえ、小夜香さんはノブを回す。
ドアをこちらに、ゆっくりと引いた。
バスルームの中も、真っ暗だった。
壁に指を伸ばし、明かりを点ける。
誰もいなかった。
小夜香さんは大きく息を吐き、再び襲ってきた薄気味悪さを持てあましながら、背筋に鳥肌を駆けあがらせた。
「念のため、入口のドアもたしかめましたが、寝る前に確認した時と同じように、鍵はかかったままでした。すごく恐かったのですが、知りあったばかりのAさんを起こすこともできません。私はベッドに飛びこむと、ガタガタと震え続けました」
結局、眠ることはほとんどできなかったという。
長い長い夜だった。
そしてようやく東の空が白々とし、新しい朝が訪れた。
だが、小夜香さんの体調はやはりすぐれない。寝不足も関係したのかもしれないが、風邪かも知れない症状まで出はじめていた。
「おかしなことに、Aさんも同じような症状だというんです。あまり具合がよくないと。頭痛がして、微熱もある。私とそっくりな状態でした」
しかし二人とも、風邪薬は携行していなかった。
小夜香さんはツアー引率者の女性に電話をし、自分もAさんもあまり体調がよくないことを伝えた。
すると引率者の女性は「風邪によく効くハーブティーを持っているから、すぐに部屋まで持っていく」と言ってくれた。
「私たちはありがたいと思いながら、彼女が来るのを待ちました。やがてドアがノックされ、迎えにでた私はロックを解除し、彼女を中に入れました。すると……」
部屋に足を踏みいれたとたん、その女性は身をこわばらせた。
そして、眉をひそめながらこう言ったという。
――ちょっと……なに、この部屋。
「私もAさんも、きょとんとしたままでした。引率の女性はしばらくの間、緊張した様子で部屋の様子を探っていました。それから私たちをじっと見て『それ、風邪じゃない。この部屋のせいよ』と言ったんです」
小夜香さんたちは、その引率者が主催するセミナーの、第0期生ともいえるごく初期の参加者だった。
フラワーエッセンスは植物のエネルギーや波動を扱うため、それに関わる人物にも敏感な人たちが多かった。
「引率者の女性もそうでした。だから部屋の状態がふつうではないことに、すぐに気がついたんだと思います」
その後、日本に帰国した小夜香さんは、陰陽師の家系に生まれ、スピリチュアルの世界で活躍をしていた友人にロンドンでの体験を話した。
すると友人は、すぐに彼女を鑑定し、
――女性だね。古い衣装を着ている。ずっと昔に亡くなった人。
そう言ったそうである。
後年、小夜香さんは改めて、プライベートでロンドンを訪れた。
そしてタワーブリッジの周辺をゆっくりと観光した際、実はそのあたりには、おどろおどろしい歴史があったことを初めて知ったという。
「あの夜、部屋に現れた女性がそれと関係があったのかどうかは、もちろん分かりませんけど」
小夜香さんのメールの最後は、そんな言葉でしめくくられていた。
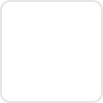


 シェア
シェア ツイート
ツイート