突然部屋の隅から現れたキジトラの子猫は…実話怪談連載「服部義史の北の闇から」第19話 猫

三浦さんはキジトラの猫を一匹飼っている。
名前は『ぬこ』という。
どんなに仕事でストレスを抱えても、家に帰ってからの癒しが彼女の救いとなっていた。
ある日のこと、帰宅してからの彼女はいつものようにぬこと遊んでいた。
ぬこは猫じゃらしが大好きなので、夢中になってじゃれついてくる。
「もーう、危ないってばー」
上手にあしらいながら、ぬこの可愛い仕草を堪能していると、突然ぬこの尻尾が膨れ上がった。
『ふぅーーーー、しゃーーーーー』
滅多に聞くことのない威嚇の声に、三浦さんは驚く。
ぬこの威嚇の対象は猫じゃらしではなく、部屋の隅にあるゴミ箱を見ているようだ。
「な、なに? 怖いってば……」
彼女は独り暮らしである為、誰かの気配に反応したとは考えられない。
「ねぇ、ぬこ。止めて、ねぇ、怖いって」
ぬこに話し掛けながらも、視線はゴミ箱の方をどうしても見てしまう。
『カタンッ……』
すると突然、ゴミ箱の陰から、乾いた物音が響いた。
ごくりと唾を飲み、全神経をゴミ箱に集中させる。
『ミャァ!』
ぬこの声ではない、か細い鳴き声が確かにゴミ箱の方から聞こえた。
「誰! なんなのよー!」
三浦さんの悲鳴に似た叫びに反応するように、ゴミ箱の陰から一匹の子猫が飛び出してきた。

一瞬唖然とするが、元来の猫好きである三浦さんは別の感情が湧き上がる。
(やだ、めっちゃ可愛い)
「おいでおいで」
猫じゃらしを揺すり、子猫の興味を惹こうとする。
その子猫はキジトラ柄で、ぬこよりは二回り以上も小さい。
先程まで威嚇していたぬこも穏やかになり、子猫と三浦さんのやり取りを眺めているようであった。
「おいあなた、どこからきたのかなぁ? 迷子なのかなぁ?」
そう言いながら手を差し伸べると違和感を覚えた。
触れようとした彼女の手が擦り抜けたのである。
(え?)
何かの間違いだろうと、何度も触ろうとするが、毛先に触れることすら叶わない。
(そうか……、きっとあなたは前の住人が飼ってた子なのね。ここで死んだんだ……)
幽霊やお化けなどは大の苦手であるが、猫となると話は別である。
可哀想にと思う気持ちと、愛らしいと思う気持ちで怖さなどは全く感じなかった。
その日は夜遅くまで、猫じゃらしで遊んであげて、次の日の仕事に備えて寝ることにした。
「ぬこ、寂しいだろうから一緒に寝てあげてね。明日も帰ってきたら私も一緒に遊ぶから」
翌日、目が覚めると子猫の姿は消えていた。
きっと満足して成仏したのだろうと、優しい気持ちになる。
穏やかなままシャワーを浴びて、化粧をし、仕事への準備を整える。
「じゃあ、ぬこ、行ってくるね。お留守番をお願いね」
アパートのドアを開けて、一歩踏み出そうとした彼女は固まる。
そして一瞬の間を置き、とても大きな悲鳴を上げた。
視線の先、私有地のところで一匹の鴉が何かを啄んでいた。
血や肉片の合間から見える所々の毛並みと大きさから、昨日現れた子猫だと気付くのに時間は掛からなかったという。
著者プロフィール
服部義史 Yoshifumi Hattori
北海道出身、札幌在住。幼少期にオカルトに触れ、その世界観に魅了される。全道の心霊スポット探訪、怪異歴訪家を経て、道内の心霊小冊子などで覆面ライターを務める。現地取材数はこれまでに8000件を超える。著書に「蝦夷忌譚 北怪導」「恐怖実話 北怪道」、その他「恐怖箱」アンソロジーへの共著多数。
★ 「北の闇から」は 北海道在住の著者がお届けするしばれる怖い話。地元で採話した実話怪談、本当にあった怪奇・不思議譚を綴ってまいります。隔週金曜日更新。
次回の更新は2/12(金)を予定しております。どうぞお楽しみに!
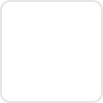



 シェア
シェア ツイート
ツイート



