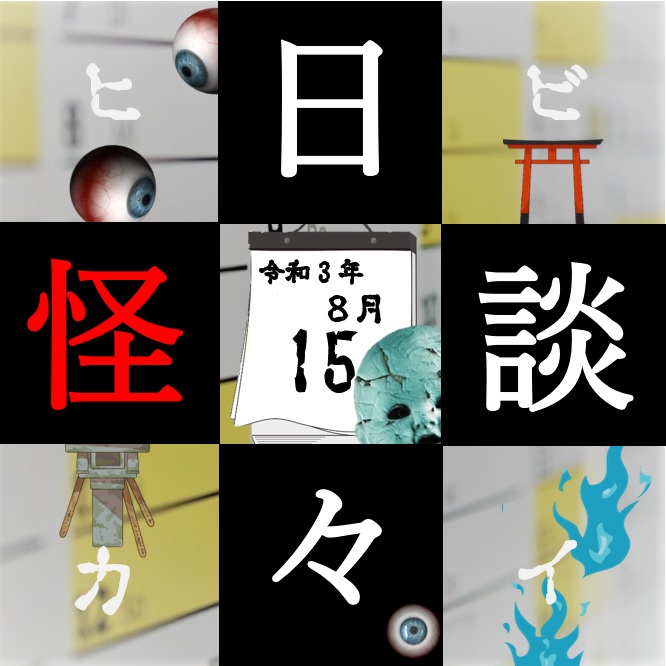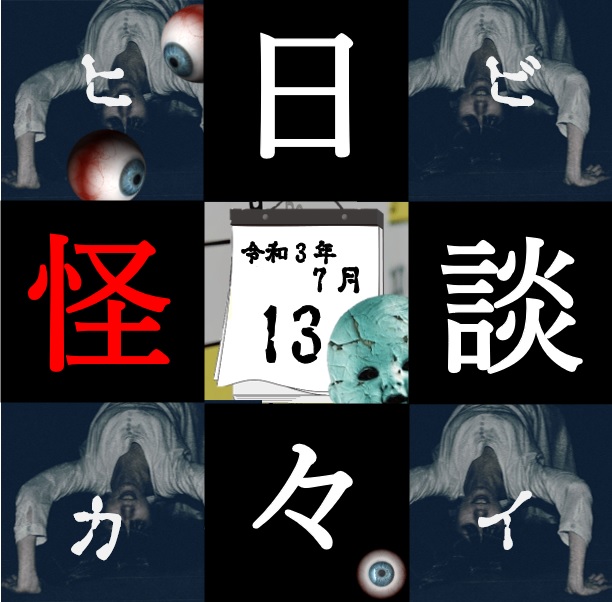【日々怪談】2021年4月15日の怖い話~ 心を込めて花束を

【今日は何の日?】4月15日: 遺言の日
心を込めて花束を
もう三十年前の話になる。渡辺さんの敷地の壁に自動車が突っ込み、下校中の大学生が自動車と壁との間に挟まれて亡くなった。
あっという間の出来事だった。
それから毎週、渡辺さんの家の壁には花束が捧げられるようになった。献花である。
渡辺さんも暫くは花束を置くようにしていた。しかし何者かが毎週欠かさずに花束を持ってきては捧げていく。ただ、捧げる一方で枯れた花束を片付ける訳ではないので、自ずとその片付けは渡辺家の仕事となった。
「またあったのよ」
妻がうんざりした顔で言った。事故のことだと直感した。
「買い物帰りの奥さんを轢きそうになって、それでハンドルを切り損ねて突っ込んだって。保険屋さんからまた連絡があるそうよ」
家の前の道では、ここ最近事故が相次いでいた。道路の見通しが悪い訳ではないし、交通量も多くない。事故を起こした車は、毎回渡辺家の壁に激突して止まる。捧げられた花束が、毎回狙われたかのようにタイヤで踏みにじられて散乱する。嫌な気持ちで渡辺さんが飛び散った花びらや包装紙を片付けると、翌日にはまた新しい花束が置かれている。
それが毎週のように繰り返された。
「ちょっと気分転換に、海のほうに美味い物でも食いに行かないか」
妻は最近ふさぎ込んでいる。口には出さないが、何かに怯えているのは分かる。あの献花がいつまで続くのか。それが続く限り事故も続くんじゃないか――。
偶然にしては気味が悪かった。この家を離れて、何処かに行きたかった。
「そうね。あなたがお仕事大丈夫なら」
妻の顔がぱっと明るくなった。久しぶりに見た笑顔だった。
旅行に出る早朝、ゴミの回収時間にはまだ間があったが、妻は生ゴミの袋を持って玄関を出た。だが彼女はすぐに戻ってきて小さな声で呟いた。
「あたし、旅行行けない……」
その場でへたり込んだ。顔から血の気が失せていた。
「おい、どうした」
肩に触れると、カタカタと小刻みに震えていた。
詳しく話を訊いたところ、妻は声を詰まらせながら話し始めた。
門を出たら、外の壁の所に老婆が立っていた。ガリガリに痩せていて、もうすぐ夏だというのにダウンジャケットを着込んでいた。
老婆は真新しい花束の前でぶつぶつ言っていたが、ゴミ収集場から戻ってきた自分に、
「この壁がなかったら! この家がなかったら! あんた達がいなかったら!」
と声を上げた。その形相が鬼のようだった。
(あぁ、あの事故のことだ。私達が恨まれているんだ)
そう気付いたら、恐ろしくなって急いで逃げてきた――。
そう嗚咽混じりに説明を終えると、
「旅行、ごめんね」
と言い残し、真っ青のまま寝床に戻った。
妻はそのまま体調を崩して寝込んでしまった。渡辺さんは仕事を休んで付きっきりで看病したが、結局半月も経たずに入院することになった。
ある朝、病院に見舞いに行こうとすると、ドアホンが鳴った。
「あなたのお宅、外から見ても分かるぐらい黒い人が沢山いる。早くお祓いしたほうがいい」
でないと手遅れになる――。
訪ねてきた見知らぬ中年女性にそう忠告された。
だが、その忠告よりも、まずは妻のほうが大事だった。
治ったら、二人で約束の旅行に行くんだ――。
気ばかりが焦った。
だが看病の甲斐もなく、妻はひと月後に帰らぬ人となった。彼女は、
「あなた、あの家を壊して。あの家から出て」
と言い残した。そのまま意識が途切れて二度と戻らなかった。
渡辺さんは、妻の遺言通り家を潰して更地にし、不動産屋に売り払った。だがその敷地を囲う壁が残っている間は、変わらずに献花は捧げられ続けていた。
「妻の見た老婆についても興信所を使って調べましたが、事故とは全く関係ない人なんですよね」
全く訳が分からなくてね――渡辺さんは目を真っ赤にして話を終えた。
――「 親切」神沼三平太『恐怖箱 百舌』より
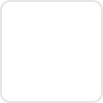

 シェア
シェア ツイート
ツイート