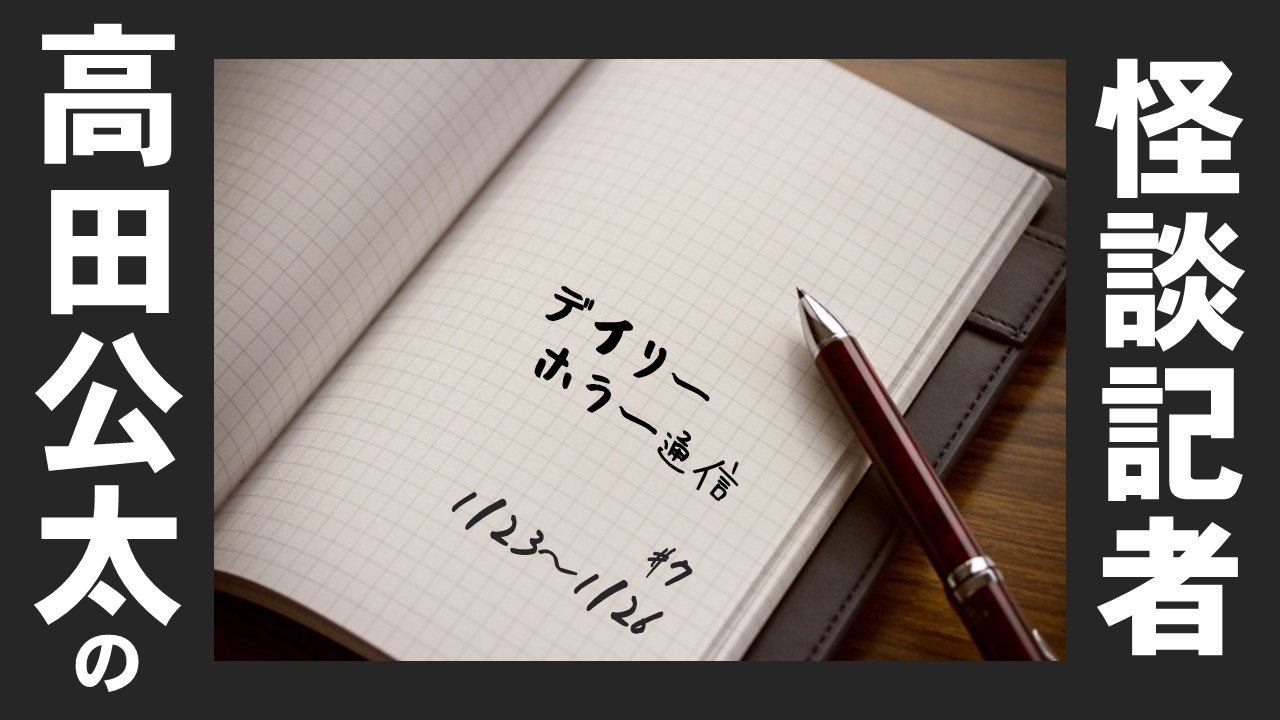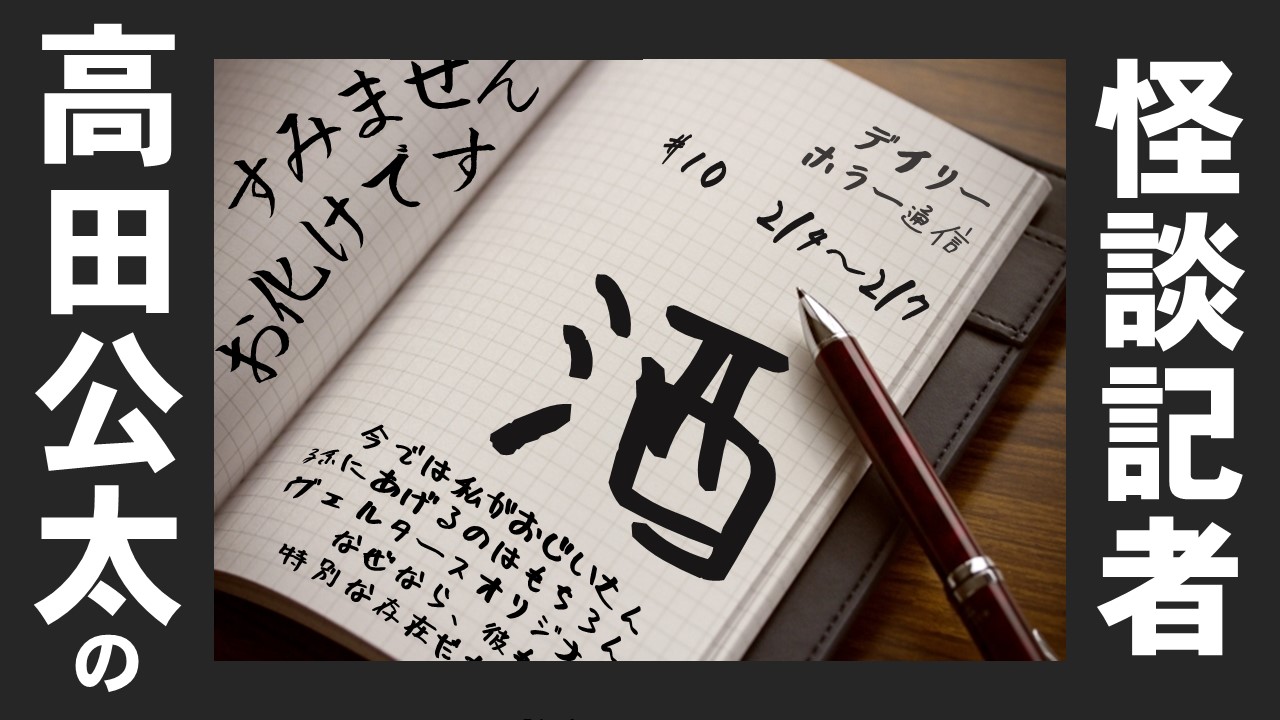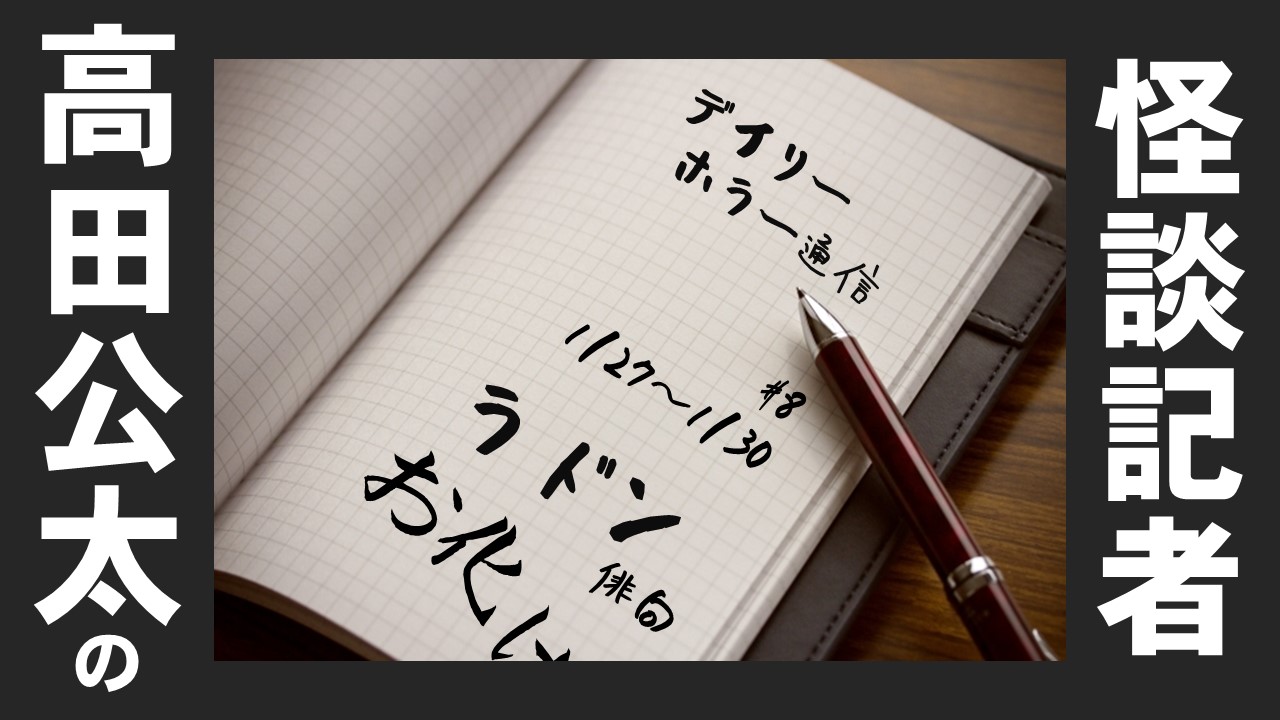【連載日記】怪談記者・高田公太のデイリーホラー通信【#18】小沢剛展/妻との馴れ初めを綴る/太宰治のような津軽の郷土作家
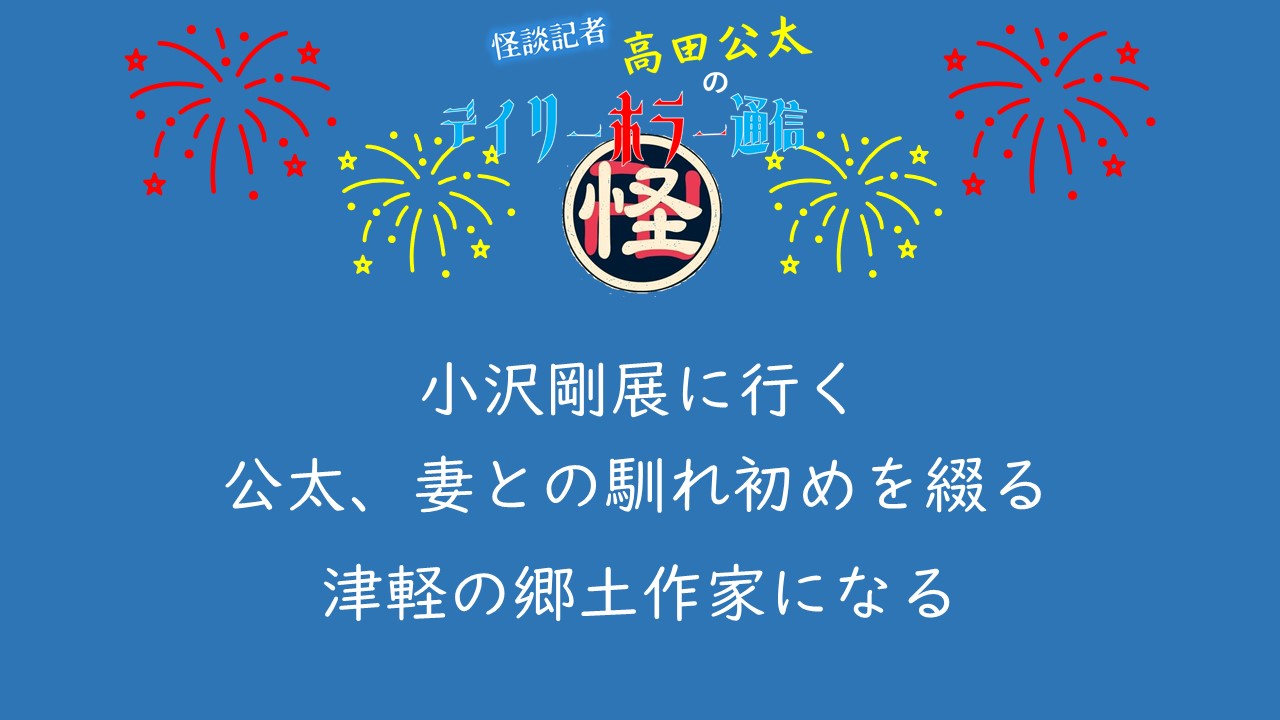
新聞記者として日夜ニュースを追いながら怪異を追究する怪談作家・高田公太が、徒然なるままに怪談・怪異や日々の雑感を書き殴るオカルト風味オールラウンド雑記帳。だいたい2~5日前の世相を切ったり切らなかったりします。毎週月曜日と木曜日に更新!
目次
2021年3月7日(日)
弘前れんが倉庫美術館で開かれた「小沢剛展」のクロージングイベントに行く。

バングラディシュ、ニューヨーク、ベルリンなどから10人がオンライン参加したトークイベントで、ラグも映像の乱れもない美術館の無線LANの太さとiMacの強さに驚愕した。
トークの中で面白かったのは、小沢さんの作風の中に「故郷」が隠れテーマになっているように思えた点。
小沢さんは都会の生まれなので、郷土感覚が希薄だという。
そんな希薄な意識を持つ小沢さんが、インドネシア、フィリピンなどで作品制作するのは、「郷土感」を求めてのことなのではないだろうか。
小沢さんの新作は寺山修司を題材とした「帰ってきたT.L.」
寺山もまた「走ってる汽車の中で生まれた」と、故郷を持たない浮遊感を表現した作家だ。
横浜聡子監督の「いとみち」、小沢剛展、「青森怪談 弘前乃怪」と、表現の仕方はそれぞれまったく違えど、共通して持つキーワードは「郷土」と「ノスタルジア」だ。
コロナ禍の中、自然発生的に「ノスタルジア」の意味が強まった感がある。
テクノロジーの発達に比例して、郷土の持つ希少価値が上がっていく。
郷土を持たない人にも、きっと郷土はある。
必ずしもなければいけないものではないが、郷土が持つ輝きに、ついつい人は惹かれてしまうのだ。
小学校の課題で、娘から手紙をもらった。
とても愛情が込められた手紙で、胸が暖かくなった。
手紙の内容は伏せる。
故郷で生きる。
2021年3月8日(月)
「青森怪談 弘前乃怪」発売初週は津軽地方で良好な滑り出し。
【速報】
— とっとこ高田ハム太郎 (@kotatakada) March 8, 2021
くまざわ書店五所川原店(複合型ショッピングセンターELM内)週間ベストセラーランキング
「青森怪談 弘前乃怪」
第1位!
青森県内の皆さん、文庫も含めた週間ベストセラーランキングを発表している書店で「弘前乃怪」がランクインしているのを見掛けたら報告お願いします~!
本屋さん巡り4#青森怪談弘前乃怪 販売していただいてる #成田本店しんまち店 様
— 弘前乃怪@青森怪談 弘前乃怪 竹書房怪談文庫2月27日発売 (@HirosakiKAIDAN) March 8, 2021
ありがとうございます❗️
青森乃怪、怪の細道もよろしくお願いします
週間ランキング二位でした pic.twitter.com/t1PwyR3iNj
Twitterでも「買いました」「面白かった」といったツイートがあり、売ってまっせ感が満載。
嬉しい限りです。
みなさん、ありがとうございます。
これは竹書房とのやり取りで決まったことではなく、あくまで個人的な作家としての目論みだが、今後は青森県の怪談は怪談愛好家グループ「弘前乃怪」及び、まだ見ぬ未来の郷土怪談作家との共著で出したいと思う。
「高田公太」だけが「青森」を背負ってしまうと、私にとっての「青森」だけが誇張されてしまい、とても恣意的だ。
故郷を見詰める目は、幾つあってもいい。
今作を編めたことは、私にとって大きな財産だった。
青森を描くにおいて、私に足りない部分を他の著者が埋めてくれた。
本書「編著ノート」でも触れたが、執筆の素人だったみんなに、随分ときつい注文を出した。
結果には満足している。
「弘前乃怪」、次作の構想も既に練っている。
リリースされるか否かは売れ行き如何のことなので、購入ツイートをまだまだお目に掛かりたいものだ。
メンタル不調のせいで、昔むかしの嫌なことを思い出して、顔を歪めることが多い。
困ったものである。
自分の半生を書き起こすのはとても難しい。
恥の多い人生を送ってきました。
これからもきっと、恥の多い人生を送るのです。
敬愛するDJ・コンポーザーのミヒャエル・マイヤーのインスタグラムで、ウルリッヒ・シュナウスのLPを見て、クワっとなりシュナウス祭り。
シュナウスはやっぱ曲が良いね。コード展開が良い。
仕事が詰まっている。
締め切りが早い方から手を付けよう。
そして、空を舞おう。
#青森怪談弘前乃怪 #ミハエルメイヤー #ウルリッヒシュナウス #メンタル
2021年3月9日(火)
一日を生きた証として、朝は平等にやってくる。
公太は胸の悪さを感じながら、目を覚ました。
布団の中からそこかしこに散らかった衣類を寝ぼけ眼で眺め、もしも今日の体調が良いようならこれらを片付けねば思う。
しかしそれはここ三日、毎朝思うことなのだが。
公太の住まいは山の方にある。仕事が落ち着いている時は、妻と娘と共にそこで過ごしているのだが、最近は街の方にある実家で寝泊まりすることが多い。というのも、山の家は街の家よりも2度ほど温度が低く、暖房器具のない山の家の自室ではとても仕事が手につかないのだ。
公太は仕事の案件が溜まるとすぐに気持ちを焦らせる傾向があった。
実際のところ、落ち着いて順にこなせば大した量ではない。それでもスマートフォンのメモ書きを見るたびに妙な不安に駆られ、「環境を変えないと、全て終わってしまう」と妻に電話をした。
そんな時妻は「はいはい。どうぞ」「分かってた。頑張って」と軽い返事を返し、公太は「ごめん」とだけ告げて電話を切った。
公太と妻はもう十年の結婚生活を迎えようとしていた。
公太と範子との初めての出会いは青森で開かれた、とあるダンス公演でのことだった。
県外のダンサー、何組かがさまざまなジャンルのダンスを披露するその公演で、範子はソロのコンテンポラリーダンスを踊り、その姿は公太の胸を打った。
その日、範子は客席から登場すると、無作為に選んだ来場客にカードを配った。
カードには「アシタ?」「ワスレタ?」などと示唆的なメッセージが書かれていて、公太が手にしたカードには「ヤクソク?」と記されてあった。
そのまま、驚くほどゆっくりと舞台スペースへ歩いた範子はドイツ由来のエレクトロニックミュージックに合わせて、公太が見たことのないダンスを舞った。
すっかり心を奪われた公太は質疑応答で挙手をして感想を述べただけでは飽き足らず、終演後に範子に声を掛けた。
「今後の公演も教えてほしいです」
話してみると範子は弘前市の生まれだが、現在は東京に住んでいるとのことだった。
公太は範子にメールアドレスを教えて、会場を後にした。
公演は二日開催で、翌日も範子のダンスに合わせて(他の出演者は口に合わなかった)観に行った。
二日目はカードをもらうことができなかったが、それでも前日と変わらず素晴らしいダンスに満足した。
その後範子からメールが来ることはなかった。
そして数年が経った頃、公太は馴染みのバーで範子と偶然再会した。
「ごめんなさい。教えてもらったメールアドレスをメモごと無くしちゃって」
その時、確かに小さなメモ用紙に買いて渡した記憶があったのでそれも仕方がないことだと公太は納得したものだが、後に範子がモノを無くす天才だということを知ってからは、その日の捉え方は変わっている。なんにせよ、重要なのは「偶然に再会した二人」であろう。
改めてメールアドレスを交換した二人は、青森と東京で盛んにやりとりをするようになった。
そして範子が公演のためにスウェーデンに滞在していた時、公太は「東京に行くから一緒に住まないか」と告げた。
範子はその誘いに応え、代々木上原での同棲生活はそのまま妊娠、結婚、出産へと繋がった。
二人の間によくあるパートナー同士のトラブルもあったが、それでもいつも二人は「幸せだね」と言い合った。
「あの日のダンスは求愛のダンスだった」公太がそう言うと、いつも範子は「まったくそんなつもりはありませんでしたが」と返した。
しかし、あの日のカードに書かれていた問い掛けは、まさしく未来を示唆していたものだったといえる。
約束だ。
そう、公太は問い掛けに応えたのだ。
生まれてきたのは女の子で、二人は彼女に「舞」と名付けた。
踊りを舞う。
舞うように生きる。
一文字に二人の思いの全てが込められていた。
公太は朝ごはんを食べてから、ウェブに掲載する原稿を綴った。
ああ、思い出が舞っている。
きっとこれからも、舞うのだ。
死ぬ瞬間にも、この煌めく翼が心を舞うのだろう。
悪くない人生だ。
公太はそう原稿を締め括ろうとしたが、思いとどまり、修正を加えた。
良い人生だ。
(了)
#私小説的
2021年3月10日(水)
うだうだと寝て過ごし、夜から仕事。
睡眠の質が良かったのか、肩こりが楽になっていた。
気心の知れた人に「うつの調子どう?」と聞かれたら「いやあ、太宰治もいることだし、作家ってのはうつになるもんなんですよ」と軽口を叩くようにしている。だいたいそれで「そうね」と済ましてくれるので、とても楽だ。
太宰先輩、ありがとう。
弘前市にある「未来屋書店 樋の口イオンタウン店」では私の書いた怪談本を「青森の本」の棚に置いてくれている。
これはとても嬉しい。
というのも、私は郷土作家に憧れがあるのだ。
太宰治「津軽」、長部日出雄「津軽世去れ節」「津軽じょんから節」と津軽を題材にした作品もさることながら、今官一、鎌田慧のような津軽ならではの「じょっぱり」とロマンチシズムを強く匂わせる作風にも郷土作家が持つ濃厚な味わいを感じる。
弘前生まれの寺山修司も、私は「津軽の人」に取り入れている。
数年前まで、自分が生まれた街にこんなにも文学的だとはついぞ知らなかった。
若い頃は田舎の「田舎臭さ」を軽蔑の対象としていたのだが、大人になってからは「田舎臭さ」が生まれる背景を理解し、受け入れることができるようになった。
正直「田舎臭さ」を受け入れることができなかった者に、田舎が耐え難い苦痛を与えていることもよく知っている。
だが、私は恵まれたことに苦痛を感じない側に立つことができた。
そうして生きると、ここを流れる大らかな空気は快適なものである。
私は「田舎嫌い」を表明する人々にあまり魅力を感じない。
どこにいようと楽しみを見出せる人のエネルギーに惹かれる。
ムラ社会だ。娯楽がない。
あなたは随分と当たり前のことを言う、没個性的な方ですね。
素晴らしい郷土作家たちが持つ顕微鏡を、私も持てるようになりたい。

夜は住倉カオスさん(フルネーム、敬称付き)とLINEで音楽談義。
こってりとしたワールドミュージックを楽しんだ。
私はここにいて、世界は相変わらず広い。
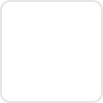



 シェア
シェア ツイート
ツイート