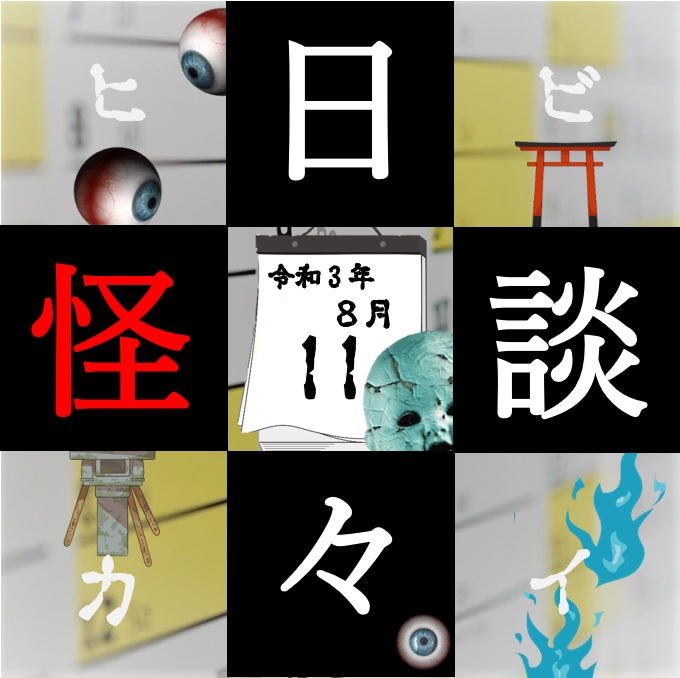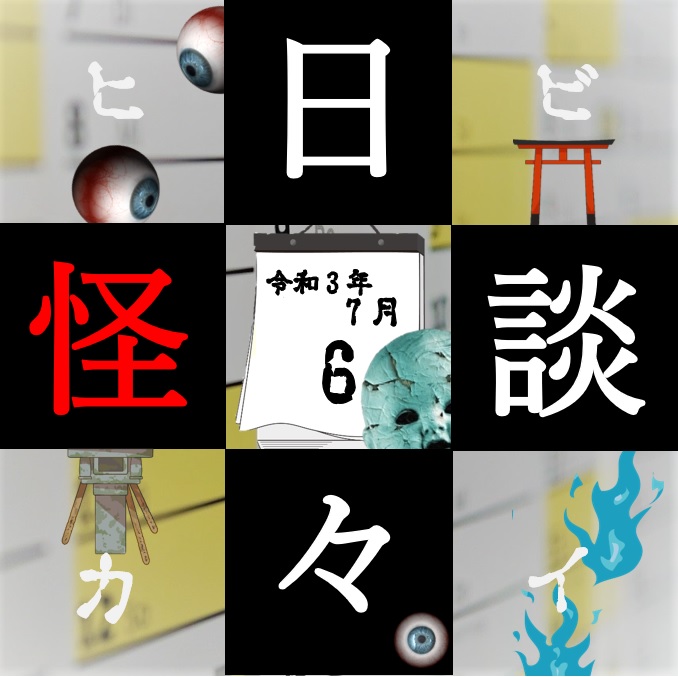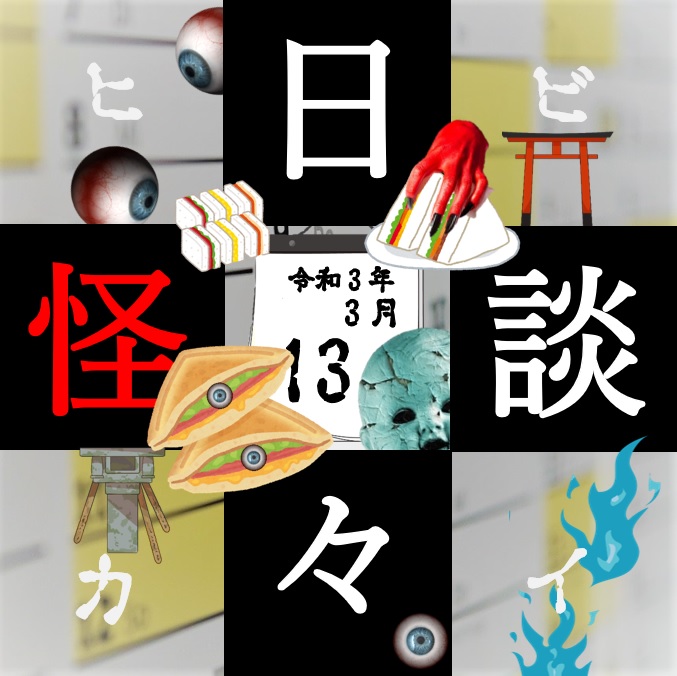【日々怪談】2021年6月15日の怖い話~サーファーと柳とラングレー
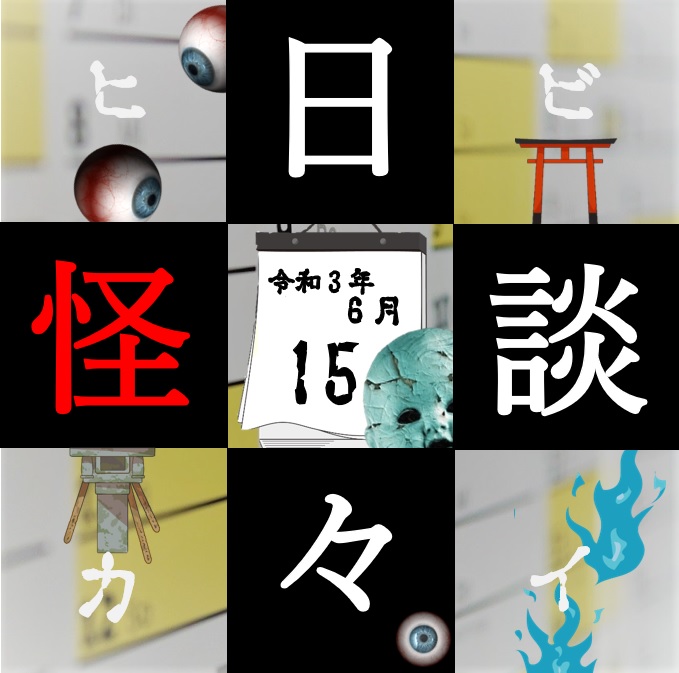
【今日は何の日?】6月15日: 千葉県民の日
サーファーと柳とラングレー
広告代理店にお勤めの野原さんが大学生の頃のお話。
当時、野原さんの所属していたサーフィン部は非常に活発に活動していた。
「まあ要するに、ちょっとでも暇があれば波を求めて海沿いへ遠征してたんですね」
フットワークの軽い部員達は合宿と称しては先輩の車にボードを積み込み、近隣の海岸を目指した。中でも都内からほど近い千葉の海には頻繁に通った。
千葉県勝浦の少し北に位置するいすみ市に、大原海岸という海水浴場がある。北に日在浦、そのすぐ先には九十九里浜の南端がある。太平洋から打ち寄せるほどよい波が楽しめる好立地で、絶好のサーフィン・ロケーションだった。
関東のサーフィン好適地のひとつだけに、野原さん達の大学以外にも方々の大学から学生サーファーが押し寄せてきていた。
このとき、野原さん達は部として海岸の近くに宿を手配してあった。
宿とは言っても浜辺の掘っ立て小屋のような長屋だった。が、学生サーファー達の目的はとにかくサーフィンのみであったので、車が駐められてボードを立てかけておけて、後は横になれるスペースがあればそれで十分だった。
浜辺の長屋に向かう道路はさほど対した舗装もされていないような一本道だった。
夕暮れ時、ボードを屋根に乗せた先輩のラングレーにすし詰めになって長屋を目指していくと、どこかの車が道路を塞いでいた。
「おい、あれ千葉商科の連中だよな」
車に積まれたボードの柄に見覚えがあった。
千葉商科大学は野原さん達のサーフィン部の隣の長屋を定宿としていたので顔見知りだったし、ボードの柄も彼らの車も見慣れている。
車はブレーキランプを点灯したまま停まっている。
スタックしているわけでもなさそうだった。
先輩は苛つきを隠さず、クラクションを何回か鳴らした。
「どうした! 早く行け! 邪魔だろ!」
しかし千葉商科の車は動かない。
「……ったく、何やってんだよ……おい、おまえらちょっと行って見てこい」
言われて野原さんと後輩達は先輩の車を降り、千葉商科の車に駆け寄った。
「後ろが閊えてんだ。早く行ってくれ!」
ドア越しに声を掛けると、ハンドルを握っていた学生はフロントガラスの先を凝視したまま、怒鳴り返してきた。
「バッ……バカ! おまえら、〈あれ〉見えないのかよ!」
言われて視線の先を追うと、そこには柳の木があった。
長屋の入り口のランドマークにもなっている大きな柳。
千葉商科の車のライトに照らし出されたその枝先で、女が首を吊っていた。
「ひっ!」
「女だよな? 首吊ってるよな?」
千葉商科の車内の全員が、柳の枝先で揺れる女を凝視していた。
そして駆け寄った野原さんと後輩の全員にも女の姿は見えた。
「先輩! この先、ヤバイっす! 逃げましょう!」
這々の体でラングレーに駆け戻った野原さん達は、先輩にそう具申した。
「はぁ? 何言ってんだおまえら」
柳の首吊り女は先輩には見えないらしく、まったく取り合ってもらえなかった。
先輩は千葉商科の車を無理矢理パッシングし、長屋に車を寄せた。こうなってしまうと、先輩が車を出してくれない以上逃げるに逃げられない。むしろどう考えても長屋の中のほうがヤバそうだった。だから怖くて長屋には泊まりたくないのだが、さりとてせっかくここまで来たのだからサーフィンはしたい。葛藤の挙げ句、先輩を除く野原さんと後輩達は、先輩のラングレーに車中泊することにした。
後輩達は先に寝落ちしていた。ナビシートで目を閉じていた野原さんも一度は眠りに就いたはずだったが、気付くと意識が戻っていた。しかし身体はぴくりとも動かない。
車内は殊の外暗く、長屋の外にある外灯の明かりすら漏れてこない。
しかし幾ら何でも暗すぎる。
〈これは――まずいんじゃ、ないか?〉
その矢先、視線を感じた。ああ、先輩が様子を見に来てくれたんだろう、と思ったが、同時に、先輩は既に一杯引っかけて泥のように眠っているだろうことも思い出した。
じゃあ、まさか。まさか。まさか。
一人、二人。三人、四人……。
幾人も幾人も幾人もの顔が、ラングレーの窓という窓全てに貼り付いている。
びしょ濡れの顔は、窓を埋め尽くしドアウィンドウ越しに車内を覗き込んでいた。
――「 サーファーと柳とラングレー」加藤一『恐怖箱 百舌』より
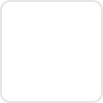

 シェア
シェア ツイート
ツイート