服部義史の北の闇から~第11話 晩酌~

森田さんは晩酌を欠かさない。
毎日、専用のグラスを凍らせてそこにビールを注ぐ。
キンキンに冷えたビールを一気に開けることで、今日も一日頑張ったと痛感するのであった。
ある日のこと、いつものようにグラスにビールを注ぐ。
さあ飲むぞ、と思った瞬間、ビールに異変が見えた。

グラスの表面についた氷越しに、綺麗な琥珀色が窺える。
その中央部分に、赤い色の靄が浮かび上がってきたのだ。
まるで赤い塗料を落としたように揺らめきながら、どんどんとビールを変色させていく。
唖然としながらその状況を見ている内に、ビールは完全に深紅に染まった。
(え……、何で?)
天井から何か液状の物が落ちてきたのかと上を見るも、特に赤い染みのようなものは見当たらない。
理解ができないまま、グラスを見据えて首を傾げる。
(どう考えても、これは飲めないよなぁ。つーか、絶対飲んじゃいけないよなぁ)
ビールが勿体ないと思いつつ、台所のシンクに投げ捨てた。
気を取り直して新しいビールを飲もうとするが、グラスは一個しか凍らせていない。
仕方がないと缶ビールのまま、飲むことにした。
一気に流し込もうとした瞬間、説明のできない違和感を覚える。
彼の本能が飲んじゃいけないと知らせ、大きく口に含んだビールを台所のシンクまで走っていき吐き出した。
やはりシンクには赤い液体が広がっている。
と同時に、呼吸ができるようになったので、口の中から鼻まで強烈な鉄臭さのようなものが駆け抜けた。
「うぅっ、おえっ、おえぇええぇ」
何度も口の中を漱ぐが、 鼻の奥に薄っすらと残る臭いは消えてくれない。
(気持ち悪い、何だってんだよ……)
森田さんはビールの不良品だと思い、缶に残ったビールをグラスに注いで色を確認する。
やはりそのビールは赤く染まっていた。
鼻を近付けて臭いを確認するが、先ほど感じた臭いがまだ鼻に残っているので良くわからない。
「これはクレームものだろ」
明日、メーカーに電話を入れようと考えるが、今日の晩酌が済んでいないので森田さん的にはどうにも収まりが悪い。
冷蔵庫から新しいビールを取り出すとグラスに注ぎ、不良品かどうかを確かめる。
「うん、これは大丈夫そうだ」
一気に飲み干そうと口に近付けていくと、またグラスの中のビールが赤く染まる。
「一体何だって言うんだよ。あれか? 空気に触れると酸化しているってことか?」
お酒が飲めないことで、森田さんの苛立ちはピークを迎えた。
そのタイミングで、森田さんのスマホが鳴る。
電話は実家の母親からで、旭川の叔父さんが亡くなったという。
その叔父さんは森田さんのことを幼少期から可愛がってくれていた。
「車の事故なんだって……。可哀想に、潰されてグチャグチャになってたんだって……」
涙声の母は必死に言葉を振り絞っていた。
「もう少ししたら家を出るから、あんたのとこに寄って、それからマサさんの家に向かうよ。ちゃんと準備をしておきなさい」
電話を切った後、森田さんは暫く呆然としていた。
(何でだよ)
その思いだけが頭の中を駆け巡っていた。
そうしていると、視界の中に赤く染まったビールが映りこむ。
無意識に眺めていると、徐々に赤い色が消えていく。
琥珀色に戻ったときに、何故か言葉が零れた。
「マサ叔父さん、あなただったのか……」
そこで漸く涙が流れた。
著者プロフィール
服部義史 Yoshifumi Hattori
北海道出身、札幌在住。幼少期にオカルトに触れ、その世界観に魅了される。全道の心霊スポット探訪、怪異歴訪家を経て、道内の心霊小冊子などで覆面ライターを務める。現地取材数はこれまでに8000件を超える。著書に「蝦夷忌譚 北怪導」「恐怖実話 北怪道」、その他「恐怖箱」アンソロジーへの共著多数。
★「北の闇から」は隔週金曜日更新です。
次回の更新は10/23(金)を予定しております。どうぞお楽しみに!
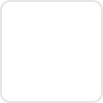



 シェア
シェア ツイート
ツイート



