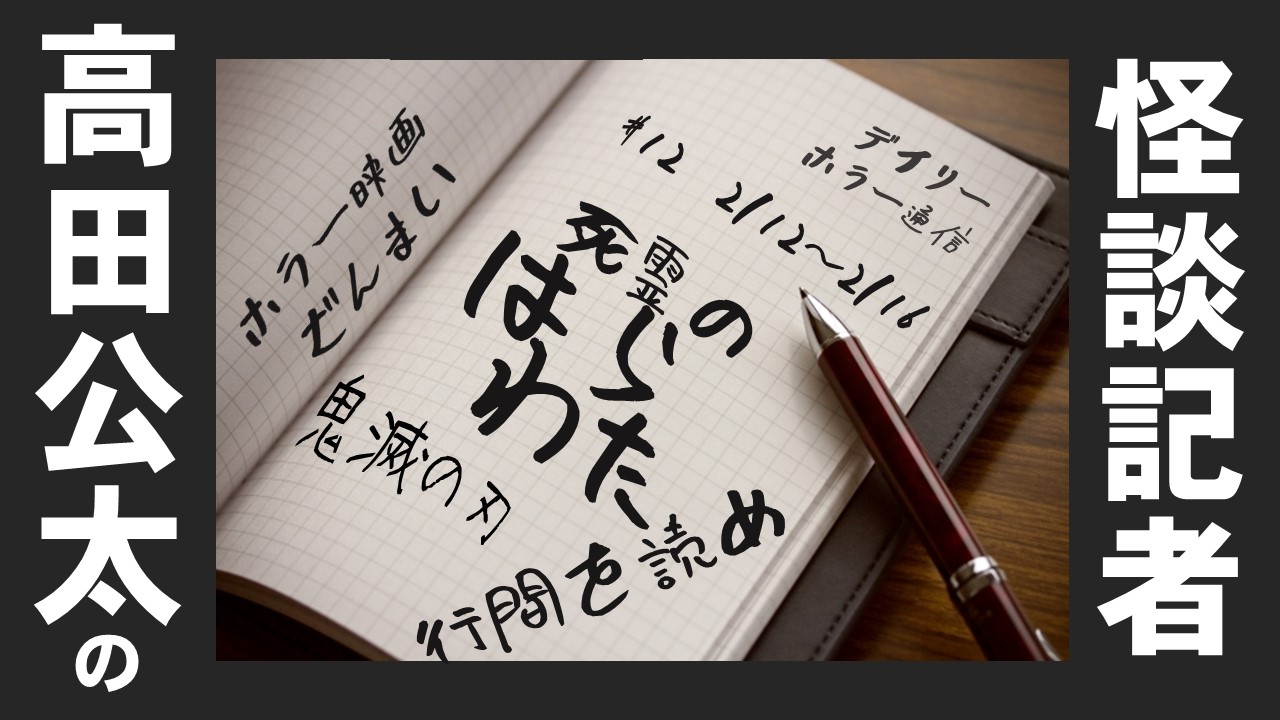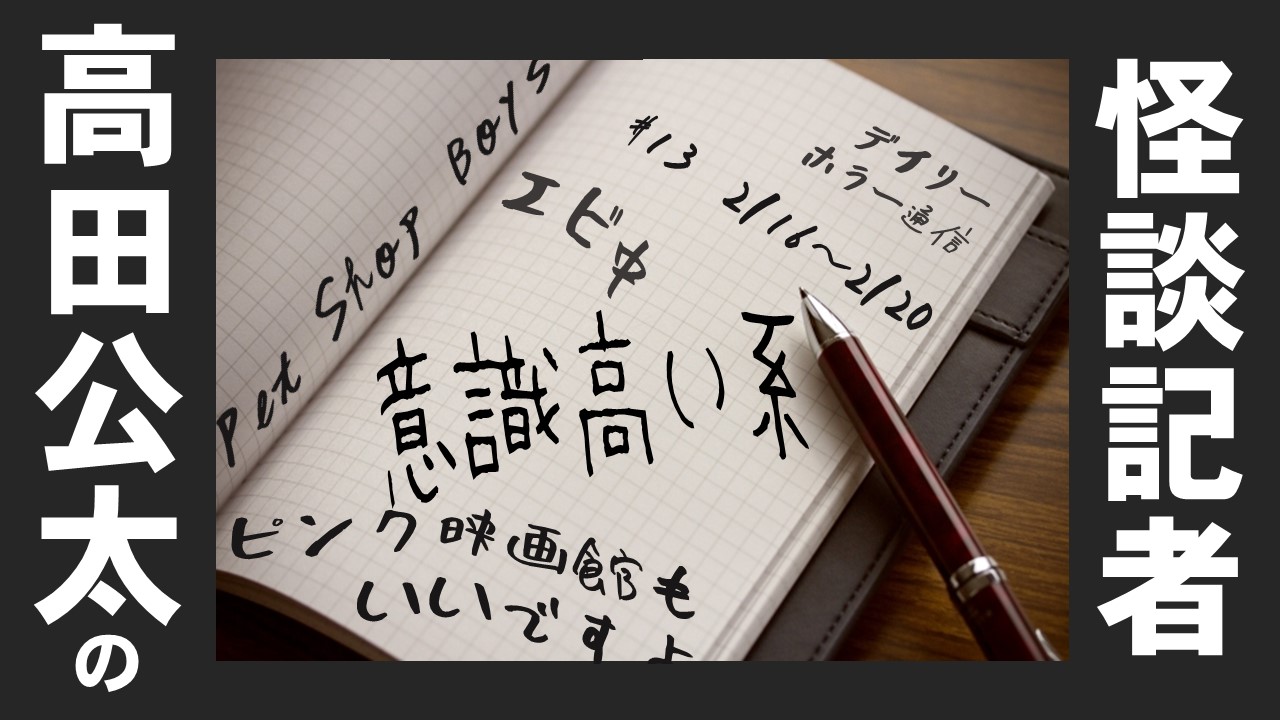新聞記者として日夜ニュースを追いながら怪異を追究する怪談作家・高田公太が、徒然なるままに怪談・怪異や日々の雑感を書き殴るオカルト風味オールラウンド雑記帳。だいたい2~5日前の世相を切ります。毎週月曜日と木曜日に更新!
■その顔 高田公太
今から五年程前に、弘前市鍛冶町のとあるスナックで、カオルという名のホステスに出会った。
カオルは当時二十歳半ばといった風体で、テーブルに着いて二言三言の会話を交わしただけで、利発で如才ない人だと分かった。
「なんか、頭良さそうだね」
私がそう言うとカオルは、
「ほんと? あたしバカだよ」
と笑ったが、聞くと都内の有名大学を卒業し、就職をしないまま帰郷した身なのだそうだ。
英語検定の二級の資格と中型バイクの免許を持ち、海外映画を観るのが好きで、読書も欠かさない。職業柄、いかにも軽そうな笑顔を振り撒いていたが、それも賢さから生まれた行いだったのだろう。
カオルもまた、私の軽薄な口調ながらも、並よりは多い映画、小説の知識に喜び、大いに酒が弾んだことをよく覚えている。
「おら、作家やってんるんず。なんも売れてないけど」
「へー。作家さんとお話しをするの初めてだ」
そうやって、カオルは私の珍妙な自己紹介をすんなりと受け止めると、続けて「どんなの書いてるの?」と、さも興味があるように尋ねてきた。
「怪談。怖い話。ホラー小説っていうよりも、本当にあった怖い話を人から聞いて、それを文章にして売る仕事」
「えー。あたし、怖いの苦手……」
カオルは眉間に皺を寄せ、そう言った。
私はその言葉から怪談話に花を咲かせるのは難しそうな毛色を感じて、戯けた顔で小さく頷くに反応を留めた。
するとカオルは私のグラスを手に取り、氷と焼酎、緑茶を足すと物言わずマドラーでそれらを掻き混ぜた。
時間にして十秒かそこらの間のことだが、私はカオルが何か考え込んでいるように思えた。
「……ない? そういう話?」
「あー……ある……いや、ない」
「ある?」
「……多分夢か、気のせいだなっていうのはある」
「聞いていい?」
「……うん」
※
カオルの家は父が代々の資産家で、生まれた時から今に至るまで、景気による変動こそあるものの、一財を絶やすことことなく生活をしている。
大学進学時は都内か海外に就職するつもりだった。
だが大学在学中に父を脳卒中で亡くしたことで、一人娘は母の傍へ戻ることに決めた。
「こっちだば(こっちだと)、働く所少ないよ」
母はカオルにいっそ働かないで、資産管理をしたら良いと提案した。
カオルもまた、それでも十二分に生活できることを知っていたので、母との時間が増えることを喜び、その通りにした。
スナック勤めは「人と触れ合いたい」から始めたのだという。
三人家族はとても仲が良かった。
自慢出来る程の信頼関係があり、親子間の思いやりも強かった。
母と比べて父は口下手で、時には小言を言ってきたものだが、それでも父を嫌いになったことはなかった。
だからこそなのか。
カオルの思い出にこんなワンシーンが強く残っている。
高校二年生の時の日曜日の昼下がり。
何となく居間に入ると、父が食卓に座っていた。
目が合うと、父は突如カオルが普段着ている学生服のスカートの丈の短さについて、滔々と意見をしてきた。
カオルはふいに説教をされたことに納得がいかず、反射的に食卓の上にあった箸立てを掴み、床に投げつけた。
今までそんな行いをしたことはなかったが、その時はなぜか躊躇なく流れるような動きでそうした。
不思議と気持ちは冷静で、暴力的な怒りというよりも、何かしらのアクションをして不満を示したいという思いがあった。
父は存外その行動に驚いた様子はなく、一度床に散らばった箸を見遣ってからは、ただ押し黙っていた。
父のそんな様子を見て、カオルはわざとゆっくり動き、テレビの前のソファーに座った。
そのままテレビを見ていると、背後でかちゃかちゃと父が箸を拾う音が聞こえた。
ああ、少し悪いことをした。
でも、制服のスカートなんてみんな短いし。
謝罪をするまでもないと判断しつつ、箸を拾うのを手伝うべきかと、食卓へ振り返った。
しゃがみ、箸を拾う父は、娘が今まで見たことのない表情をしていた。
考え込んでいるような。
放心しているような。
小刻みに震える手は、何かを我慢している印象を与える。
立派な父が、小さく見える。
ごめんなさい、と言えたら気も楽になるのだろうが、喉から言葉が出ない。
見てはいけないものを見てしまった。
カオルはテレビに視線を戻し、父が居間から出ていくまで、自分の心臓の音を聞いていた。
※
父の葬儀は沢山の人の涙で濡れていた。
誰よりも母と娘が涙を零し、その姿が葬列者にさらなる涙の雨を降らせた。
大学の卒業式が近くなった頃、カオルは母に帰省の意思を告げた。
娘の思いを察した母は「あなたがそれで良いなら」と、言葉少なく受け入れた。
そして弘前に戻った初日のこと。
在学時に購入した家財などを自室に入れ、夕方から母とゆっくり晩酌を交わしていると、疲労のせいか二人とも早めの就寝となった。
「お母さん、おやすみ。朝ごはん、あたし作るはんで(作るから)」
「ありがとう。おやすみね」
母は一階の寝室、カオルは二階の自室へ向かう。
一階のダブルベットではかつて三人がそこで眠り、やがて二人となり、今は一人だ。
受け入れているはずの父の死に、ほんの少しだけ抗いたい気持ちが湧き上がるのを感じつつ自室のドアを開け、ドアの横にある電灯のスイッチを入れた。
蛍光灯の明かりはいつもより、随分と白っぽく点き、八畳の部屋の中、ベッドと机の間に父が立っていた。
急に現実味が失われる。
既に夢の中にいるとしか思えない。
思うように手足が動かなくなり、目の前の父と自分の距離感が掴めなくなる。
カオルは身体を左右に揺らしながら、ぼんやりと父の姿を眺めるほかなかった。
大好きなお父さん。
まるで子供に戻ったような心持ちで、そこに佇むだけの父の顔をじっと見詰めた。
ああ、見たことのある表情だ。
そうだ、あの時の表情だ。
あの日、箸を拾っていた時の何ともいえない顔つきがそこにあった。
これは。
ああ。
今なら分かる。
お父さんは困っている。
きっと、私の振る舞いに困っているんだ。
お父さんは正しいのか間違っているのかも分からず、現状に答えを見つけられないまま、困っている。
そうか。
あの日も困っていたんだ。
私に困っていたんだな。
お父さん。
カオルはそれが声になっているのか確信を持てないまま、父に必死に伝えようとした。
お父さんのせいじゃないよ。
あたしは帰ってきたくて、ここに来たんだよ。
やりたいこともなかったし、これで良いんだよ。
お父さんが死んだせいじゃないんだよ。
これで良いんだよ。
あたしは本当に幸せなんだから。
父はまだその顔でこちらに向いている。
だから、気にしないで。
そんな顔、しないでよ。
あたしも、困っちゃうよ。
カオルがそうやって、伝えても。
父はまだその顔のままだった。
※
朝、目覚めるとベッドの上だった。
結局はただの夢だったようだ。
少なくない量のアルコールを摂っていたので、あんな曖昧な現実に遭遇したのだろう。
一階に降りると、母が朝食を作っていた。
「ああ、ごめん。寝坊してまった(寝坊してしまった)」
「おはよう。別にいいわよ」
「お父さんの夢見たよ」
「えー。カオルも? お母さんも見たよ」
「お母さんも? 家族揃ったから、お父さんも寂しくなって出てきたのかな」
「かもねえ。お母さんは、お父さんにずっと手を握ってもらう夢を見たの」
「へえ。良い夢だね」
「そうね」
カオルの脳裏に、昨晩の父の「その顔」がリアルに浮かんだ。
本当に夢だったのだろうか。
「お母さん」
「ん?」
「お父さん、どんな顔してた?」
「どんな顔って……ただ手を握られた感触があっただけだから、顔は見てないけど……」
「そっか」
「でも、手は温かったわよ」
「そっか」
お父さんの温かい手と「その顔」。
きっとお父さんはこれからも、あたしに困りながらも、温かい手で傍に居てくれるんだ。
うん。
帰ってきて本当に良かった。
ただいま。
お父さん。
おかえり。
カオル。
(了)
※プレイリストはお休みします
 ▲連載一覧▲
▲連載一覧▲書いた人
高田公太(たかだ・こうた)
青森県弘前市出身、在住。O型。実話怪談「恐怖箱」シリーズの執筆メンバーで、本業は新聞記者。主な著作に『恐怖箱 青森乃怪』『恐怖箱 怪談恐山』、『東北巡礼 怪の細道』(共著/高野真)、加藤一、神沼三平太、ねこや堂との共著で100話の怪を綴る「恐怖箱 百式」シリーズがある。Twitterアカウント @kotatakada 新刊『青森怪談 弘前乃怪』2/27発売!

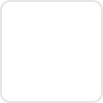




 シェア
シェア ツイート
ツイート