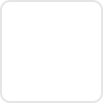竹書房怪談文庫TOP新黄泉がたり黄泉つぎTOP新黄泉がたり黄泉つぎ一覧サボテン
新黄泉がたり黄泉つぎ
「サボテン」
「……昔のことなんですけど、同僚にいなくなっちゃった人がおりまして」
近畿地方の大学に勤める檜山さんは、かつて委託社員として大学で働いていた哀川さんという女性事務員の話を教えてくれた。
「これ捨てちゃうんですか。可愛いのに」
会議の帰りに、哀川さんは様々なガラクタが寄せられた一角で足を止めた。
年度末の大掃除の結果、不用品と目されたものが事務室の廊下に出されているのだ。
「ああ、欲しいものがあったら持っていっていいよ。どれも明日には業者に持っていってもらっちゃうから。今のうちにね」
「それじゃ、私このサボテンのミニ鉢をいただいてもいいでしょうか」
誰が置いたのか鉢植えのサボテンが捨てられていた。直径にして五センチ程度だろうか。その上にコロンと丸い緑色のサボテンが植わっている。檜山さんには、その鉢のサイズが二号鉢だという知識がある。若い頃にサボテンを何度か買い求めたことがあるからだ。ただ、当時買い求めた鉢にはもう何も植わっておらず、庭の隅に重なって放置されている。一年と経たずに枯らしてしまったのだ。
「サボテン、育てるの難しいですよね」
「え、そうなんですか。水もあまりあげなくていいし、簡単だとばかり思ってました」
哀川さんはサボテンどころか、今までに鉢植えの植物を育てたことはないのだと、はにかんだような顔で打ち明けた。
「実家には小さい庭もありましたし、母は庭いじりも好きだったんですけどね」
自分にはまだ植物と向かい合うのは早いと思っているうちに、そのまま社会人になり、アパートで一人暮らしをはじめるようになり、結局庭仕事にも植物を愛でることとも縁遠くなってしまったのだという。
数年前に母が亡くなり、そのまま実家の庭も荒れ放題とのことだった。
哀川さんの心の柔らかい部分を晒されているような気分になって、檜山さんはその場を逃げ出したくなった。
「――世話をしてあげる人がいないと、植物もかわいそうですよね」
それには同意できた。
鉢植えを持ち帰った翌日から、哀川さんの様子がおかしくなった。物思いに憑かれたかのようで、話しかけても反応が鈍い。
さらにぽつぽつと休みがちになった。無断で休まれては困ると事務長からも注意を受けたが、一週間と経たずして仕事に全く出てこなくなった。今までの真面目な務めっぷりからは想像できない変わりようだった。どうやら連絡を入れても繋がらないらしい。
これは急な病気で入院でもしているのではないか。それにしたって連絡の一本くらいは入れる余裕はあるだろうに。
年度末から新学期という大学の事務が最も忙しい時期である。予告なく一人欠けるのは負担が大きい。正直困ったものだと周囲は思っていた。
彼女のアパートは大学の最寄り駅のすぐ近くだ。以前一緒に帰った時に教えてもらったので、檜山さんは場所を知っている。
お見舞いに行ってみるべきかしら。
自然と足がそちらに向かった。彼女の住むアパートの窓は明かりが灯っていなかった。
やっぱり留守にしているんだ。
鉄製の階段を上ると、暗い蛍光灯の光の下で、哀川さんの部屋のドアが半開きになっていた。檜山さんは吸い寄せられるように扉に近づいていく。
チャイムを鳴らしても返事はない。そもそも人の気配がない。
やっぱり入院でもしているのかしら。まさか、部屋の中で亡くなっているとか?
そう思うと、いても立ってもいられない。悪いと思いながらドアを開けた。キッチンの先に部屋が続き、一番奥側のカーテンの隙間から、街灯の明かりが差し込んでいる。ぼんやりとしたその光で、何か沢山のものが床に置かれているのがわかった。
ドアの脇に手を伸ばし、指先で探るようにしてスイッチを点けた。
眩しいほどの光量で電球が灯った。その照らし出した光景に、檜山さんは絶句した。
床にびっしりとサボテンの鉢植えが敷き詰められていた。百や二百では収まらない数のサボテンの鉢が、キッチンも奥の部屋も埋め尽くしていた。
その一番奥に、かろうじて何も置かれていない空間があった。縦長のその空間までたどり着くまでには、鉢を退かしていかなくてはいけない。
檜山さんは夢中でサボテンの鉢を退けながらその空間にたどり着いた。
空間は人型をしていた。
その心臓に当たる部分に、哀川さんが拾っていったサボテンのミニ鉢が置かれていた。
★次回は営業のKさんです。どうぞお楽しみに!
●神沼三平太さんの新刊はこちら!⇒「実話怪談 寒気草」