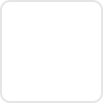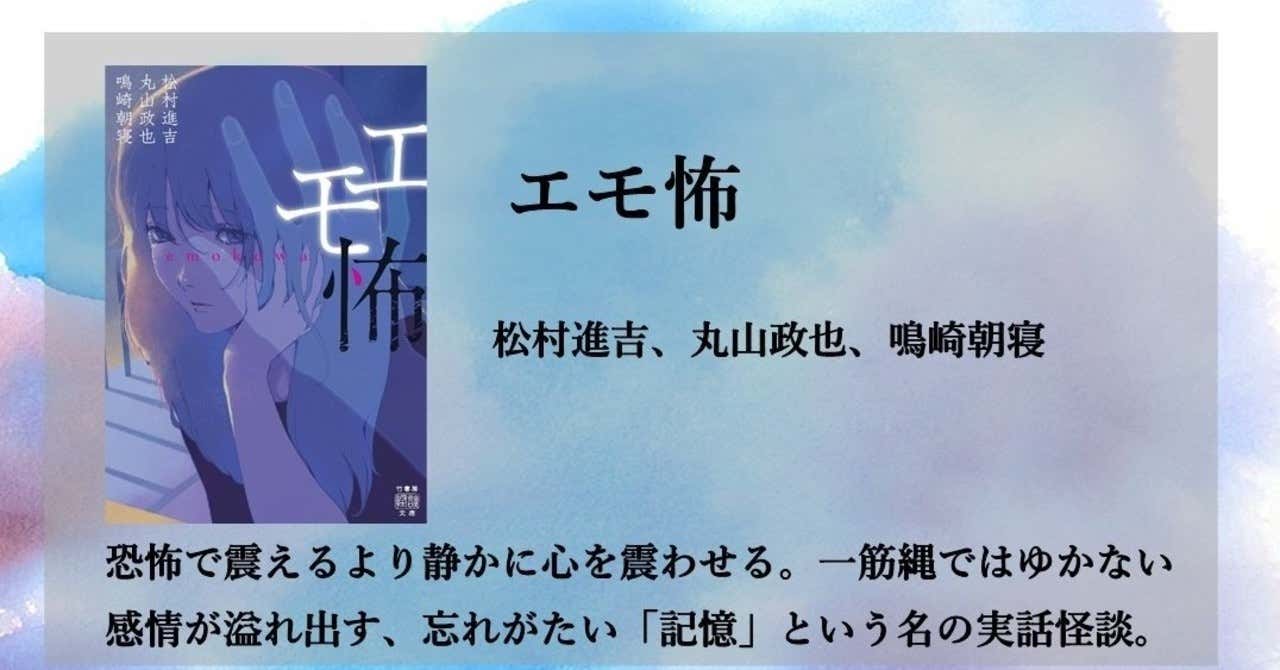竹書房怪談文庫TOP新黄泉がたり黄泉つぎTOP新黄泉がたり黄泉つぎ一覧不詳の親族
新黄泉がたり黄泉つぎ
「不詳の親族」
そろそろ還暦を迎える北村さんが小学生の頃というから、今から五十年ばかりも前の話になる。
「……当時、私の実家の母屋には親族が集まる時のための、ふた間続きの部屋があったんです」
それほど大きな家ではなかった、と彼女は言うが、田舎の家はどこも広い。
北村家にも普段はほとんど使わない十二畳の和室がふたつ、母屋の東側に並んでいた。
片方の部屋には床の間があり、いわゆる客間であるが、仏壇も置かれている。
もう片方の部屋は、押し入れに座布団などが仕舞ってあるだけで、家具も調度品もない完全な空室。
「法事とかになると、その間の襖を取っ払って、ひと部屋として使うんです。……でも、そうやって集まる親戚もどんどん高齢化して、ちょっとずつ減っていってしまって」
北村さんのお兄さん――現在の母屋の主は、家屋の老朽化によって建て直しを迫られた際、間取りを大きく変更することにした。
無用な空間を取るよりも、そのぶんリビングを広くしたほうが良い、と考えたのだ。
なので現在は、かつてのようなガランとした客間は残っていない。
「正直、少しホッとしてるんですよね、私。子供の頃は、あの仏壇の部屋が怖くて――」
仏壇が置かれた客間の、壁の高い位置に、七、八枚の遺影が飾られていた。
いずれもモノクロで、しかめつらしい顔をして虚空を睨んでいた。
いや――幼い北村さんとしては、そんな風に感じられた。
それらが既に故人の、近い身内であることは承知していても、彼女の知らない大人達であることに違いはない。会話した覚えもなければ、名前すら定かではないのだから、ほとんど他人と変わらない。
そのため、北村さんは仏壇の部屋に入るたび、自分の家の中なのに、まるで余所の人が居座っているかのような違和感を覚えずにはいられなかった。
――中でもひときわ気になるのが、部屋の南西の隅に飾られた、一枚の写真。
それは最早違和感というより、異物感に近い。
明らかに異様な感じがする。
どうして、こんな人の写真が飾ってあるのだろう――。
「……男性の遺影でした。ちょっと年齢はわからないんですが――とにかく髪も眉もなくて、ひょっとこみたいに口を尖がらせてるんです。笑ってるのか泣いてるのかよくわからないところも、本当にひょっとこみたいでしたね」
北村さんは、その写真が怖かった。
あれは誰だと訊いても、家族は「昔の親戚だ」としか言わない。
名前すら教えてくれない。
母屋に飾ってあるくらいなので、かなり近い血縁者の筈ではあるが、それが父の兄弟なのか、祖父の兄弟なのか、はたまた曽祖父の兄弟なのかもわからない。
「で、その写真にはもうひとつ違和感があって、よくよく見てみると首から下が〈絵〉なんです。ちょっとだけ斜めを向いてる感じでしたけど、顔だけは写真で、その下の喪服はその時のポーズに合うように、上から描き込んでありました」
どうしてあの人の服だけ絵なのかと訊くと、両親も祖父母も途端に機嫌を悪くして、理不尽に怒り出した。
北村さんのお兄さんが訊いても、妹さんが訊いても、それは同様であったらしい。
なんとも不可解な話であるが、彼女が本当にその写真を恐ろしく思ったのは、小学五、六年生頃のある晩のこと――。
――シャシャシャシャシャシャシャシャシャ……
――シャシャシャシャシャシャシャシャシャ……
夜、便所に起きた北村さんは真っ暗な仏壇の部屋から、奇妙な音を聞いた。
何かが擦れ合っているような一定のリズム。
怪訝に思い、廊下の電気をつけたまま、そっと襖を開けると。
部屋の中央の畳の上で、黒い額縁が素早く回転している。
思わず「あっ」と声を出すや否や、その額縁はシャシャシャ――シャシャシャ――シャ――と速度を緩め、ほどなくぴたり、と停止した。
ひょっとこ顔の遺影だった。
彼女はゾッとして、男兄弟が寝ている部屋に逃げ込み、兄の布団で一緒に寝かせてもらったという。
「母屋を建て直す時に、あの遺影は捨てたって言ってました。ひとりふたりと年寄りの親戚が亡くなっていって、とうとう本当に、あれが誰なのか知ってる人がいなくなったので……」
潮時だろう、という話になった。
なのでその男性の正体は、最早永遠に、不詳のままである。
新しい仏間には、遺影は一枚も飾っていないという。
★松村進吉さんの新刊はコチラ➡『エモ怖』
★人気作家書き下ろし怪談リレー「黄泉がたり黄泉つぎ」が新しくなりました!
「新・黄泉がたり黄泉つぎ」では当月の作家さんが来月の作家さんへ「お題」を出します。
来月の方はその「お題」にそった実話怪談を披露していただくことになります。
誰がバトンを受け取ったかは更新までのお楽しみ!
第8回・緒方あきらさんからのお題は「和室」でした。いかがでしたか?
さて、第9回・松村進吉さんからのお題はこちら!→「悪夢」
どうぞお楽しみに。