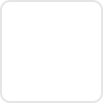竹書房怪談文庫TOP新黄泉がたり黄泉つぎTOP新黄泉がたり黄泉つぎ一覧虫頭
新黄泉がたり黄泉つぎ
「虫頭」
明美には、幼い頃の奇妙な記憶がある。
彼女が小学校に上がるまで近所に住んでいた、幼なじみのA子。そのお母さんにまつわる記憶だ。
明美とA子の家は、同じ通り沿いに並んでいた。そのため、物心ついた頃から、よく二人で遊んでいたものだった。
そして外から帰る時はほぼ必ず、手前にあるA子の家のそばを通ることとなる。
そこは小さな一軒家で、いつも台所の窓が開きっぱなしになっていた。だから夕方すぎには窓ごしに、夕飯の支度をするA子のお母さんが見える。
しかし、いつからそうなってしまったのだろうか。
その窓からはいつも、大きな虫の頭がのぞくようになった。
大きな目とアゴ。アリのようで、バッタにも似た、昆虫のような顔。
そんな「虫頭」が、台所の中にしれっと立っている。
しかし首から下は、見覚えのあるエプロンをした人間の体なのだ。そしていつも、A子が窓に向かって「ただいまあ!」と声をかけると、虫は彼女のお母さんの声で「はーい」と返事する。
……なんだかよくわからないけど……あれはA子ちゃんのお母さんなんだろう……
今から考えれば異様な光景だ。しかしまだ幼い明美は、そういうものだと受け入れてしまっていた。
もしかしたら、これはそんなに変なことじゃないのかもしれない。他の子たちの家だって、台所の窓から見えるお母さんは、けっこう「虫頭」なのかもしれないし……。
そしてA子の母親が虫に変わるのは、夕方に台所の窓からのぞいた時だけ。晩ご飯の用意をしている、そのタイミングだけだった。外で会ったり、朝の登校時には、当たり前にいつも通りの、「お母さんの顔」をしている。
とはいえもちろん、明美の中でも違和感がない訳ではなかった。
「どうしてA子ちゃんのお母さんは、ときどき虫になるの?」
自分の両親にそう聞いて、笑われたりもした。あまり何度もたずねたので、ついにはひどく怒られたりもした。「そんなこと、家の外では絶対に言っちゃダメだぞ」と。
だからA子にも、「虫頭」ついてはなにも質問してないはずだ……たぶん。
そんな日々がしばらく続いた。小学生になり、他の子たちとの付き合いも深くなれば、おそらく明美もこれが異常な現象だと、はっきり気づいたことだろう。
しかしその前に、台所の「虫頭」は思わぬ形で途切れることとなる。
ある日突然、A子のお母さんがいなくなってしまったからだ。
事故や病気で亡くなったのではない。後で大人たちから聞いた話では、どこか遠くに、知らない誰かと逃げていってしまったらしい。
それからはA子と遊ぶ機会も少なくなり、お互いなんとなく疎遠になっていった。
そして小学校に入学するタイミングで、A子と父親は、他の街へと引っ越していったのである。
空き家となった彼女の家は、誰かが代りに住むこともなく、かといって取り壊されることもなく、ずっと放置され続けた。壁はだんだん薄汚れていき、庭も雑草だらけになっていく。
A子の家が廃墟となっていく様子を、明美は何年も何年も眺め続けていた。
そして明美が高校生になった夏。八月中頃の夕暮れ時。家へと帰る途中のこと。
A子の家の近くにさしかかったところで、ふいに明美の視線が下へと動いた。
チカリ、と灰色の道路の上で、小さな赤い光がきらめいたからだ。
なんだろう、と屈んでのぞきこむ。
「あっ」
口から叫び声がもれた。
あの虫だ。
六本足で真っ赤な体をした虫が、ヨタヨタと道を横切っている。胴体はまったくなじみのない色形をしていたが、その頭だけは確かに見覚えがあった。
十年くらい前、何度も何度も見ていた、アリとバッタの中間みたいな顔。
まぎれもなく、夕暮れのA子のお母さんの「虫頭」そっくりだったのだ。
捕まえようかと迷っているうち、赤い虫は、かつてA子が住んでいた家の庭へと入っていった。
あわてて雑草をかきわけてみたが、虫はそのまま、伸び放題の草の下にまぎれてしまった。
空の色はもう、夕焼けから青黒い夜へと変わっている。
足元はすっかり暗く、草むらの中の小さな虫など、とても見つけられそうにない。
あきらめて道路に戻った明美は、とぼとぼと我が家へ歩きはじめた。
――あのお母さんは、今日、どこか遠いところで、死んじゃったんだろうな。
なぜだか無性に、そう思えてならなかった。
★吉田悠軌さんの新刊はコチラ➡「恐怖実話 怪の残響」
★人気作家書き下ろし怪談リレー「黄泉がたり黄泉つぎ」が新しくなりました!
「新・黄泉がたり黄泉つぎ」では当月の作家さんが来月の作家さんへ「お題」を出します。
来月の方はその「お題」にそった実話怪談を披露していただくことになります。
誰がバトンを受け取ったかは更新までのお楽しみ!
さて、第1回吉田さんからのお題はこちら!→「タブー」
どうぞお楽しみに。